ああ、初恋!
誰もが一度は通る、はかなくも忘れ難き小径。
そして旅立ち。出会いと別れ。懐かしき日々。
昭和から平成、令和と時代は移り行くとも、人の本質は変わらない。
時は刹那も留まることなく、人々は生老病死から逃れられぬが故に、人の世はいつも混沌だ。
そんな無常の世でも、楽しく生きる術はある。
忘れ難き日々と現在を気ままに旅し、思いのままを吐露する。
- マクロンに我が友・所英樹の爪の垢を煎じて飲ませたい?
- 初恋
- 忘れられない神々しさと哀愁
- ゴム長の青春
- ひろみちゃんを必死に口説いた日
- 男と女
- 「山のあなた」と「見果てぬ夢」
- バンコクの別れ
- かぐや姫はウイーンに行ってしまう
- 初めての観劇
- 初めての観劇:木琴をたたく少女
- 覚悟の告白
- ビックリ仰天!彼女の過去
- 寂寥
- 空の上の仕事人
- おばさん構文とマルハラ
- 厨房男子の造った三升漬
- まだ見ぬ女(ひと)
- 『山線』に乗ってみたい!
- ババ自慢
- 潮太鼓と男たちの望郷
- 阿吽
- 小樽潮まつりの「ねりこみ」を完成させた、たった一言の威力
- 阪神・淡路大震災と取り立て屋K
- 学閥
- 銀座は後か、それとも先か?
- インターネットラジオ
- 『箱根駅伝』と『はやぶさ』
- 懐かしいたった二度の会話
- あの大波はどうして、たった一度だけ押し寄せたのか?
- イワナは何匹釣れた?
- 果たして駅名は?
- 喜怒哀楽
- とん平の天津麺
- 「君はボクシングの他にやりたいことがあるか?」「はい、あります」
マクロンに我が友・所英樹の爪の垢を煎じて飲ませたい?
フランスのマクロン大統領が掲げる政策の一つに『多文化主義』がある。
しかし、マクロンは世界的な暴力集団シーシェパードの親玉、ポール・ワトソンを匿った。
ワトソン容疑者は、「反捕鯨」を掲げ、危険で悪辣な暴力を用いて捕鯨やサメ漁、イルカ漁を妨害し続けた犯罪者である。
鯨の肉食は日本の食文化だ。
サメを食すのはコスタリカの食文化だ。
これを認めず、国際手配されていた海のテロリストを無法に匿って何が「多文化主義」だと言いたい。
マクロンを支持するパリ市長はワトソンに「名誉市民」の称号まで与えた。
開いた口が塞がらない。
「多文化」政策を声高に叫ぶフランスが、国を挙げて他国の「食文化」を否定するのだ。
マクロンの矛盾は、これにとどまらない。
合法な政党である『国民連合』を危険な極右と決めつけ、ことさらに非難するのも、国民連合が排外主義だからなのだと言う。
しかし、マクロンは再選を目指した大統領選の直前に、移民やイスラム教徒に対して厳しい姿勢へと急転換した。
排外主義だと毛嫌いする国民連合の政策を、そっくりそのまま盗んだのだ。
これは、自己保身に走った大統領が「極右を真似た」と、多くの国民から喝破されている。
マクロン大統領の言動には、「フランス中心で傲慢だ」「特定の民族に対しての差別的な発言はあまりにも傲慢」との批判も絶えない。
腐っても大統領である。
権力者である。
自己保身に傲慢がくっついたら、どうなってしまうのやら。
フランス国民は、アメリカの大統領を非難している場合ではないだろう。
その点、我が友・所英樹は違う。
信念の人である。
情の人である。
熱い男である。
自己保身とは縁のない男である。
世界で唯一の捕鯨母船を有する『共同船舶』の社長、その人が所英樹だ。
ポール・ワトソンやマニュエル・マクロンと相容れないのは言うまでもない。
昨年12月、久しぶりに所さんと会った。
世界でただ一隻しかない捕鯨母船「関鯨丸」とキャッチャーボートが石狩湾新港へ寄港するのに合わせ、クジラ肉の宣伝と記者会見を行うため北海道へ来たのだ。
一日目の夜は、札幌すすき野で飲んだ。
社員や広報関係の方も同席したが、仕事への情熱と人柄の良さは相変わらずだ。
酒席では、グリーンランドで身柄を拘束されていたポールワトソン容疑者について少しだが、触れる場面もあった。
二日目は、社長自らが『関鯨丸』とキャッチャーボート内部を案内してくれたのだが、驚きの連続だった。
船内の設備につては隅々まで把握しているし、性能や機能まで実に詳しく説明してくれるのだ。
船長をはじめ、乗組員には「ご苦労様」と、これまた丁寧に労うのだった。
彼は公認会計士であり、スタッフ十数人の税理士事務所を経営している。
だが、共同船舶の社長を引き受けた数年前から、税理士事務所の運営は部下に任せきりだ。
今は共同船舶の社長業に専念しているのだという。
「鯨をたくさん食べていた昭和30年代の日本はとても元気だった。だから、今こそ鯨を食べて日本を元気にしよう」
このフレーズを掲げ、八面六臂の活躍を続ける。
そして、彼の信念と人柄を良く表しているのが、共同船舶のホームページに記された次の文面だ。
『持続可能な捕鯨を実現するために、最も大切なのは「人」だと考えます。
企業理念においても、まず第一に従業員について触れていることから、私たちの価値観を理解いただけるのではないでしょうか。』
人を愛し、人を育て、人を大切にするのが所英樹である。
『所会計:現TOWA』は東京新橋の駅前に建つ会計ビル9階にある。
2011年(平成23年)3月11日の午後だった。
東日本大震災に襲われ、古い会計ビルは洋上をさまよう小舟のように揺れる。
かつて経験したことのない、激しく長い揺れだ。
多くの人たちは、揺れの合間にビルの外へ逃げだした。
筆者も何とか9階の応接室から非常階段を降りることができた。
だが、所英樹社長と一部スタッフは、大きく動揺する9階事務所に最後までとどまったのだ。
後にその理由を聞いた。
「尊敬する両親から引き継いだビルだ。最後まで見届けたかった。もし、倒壊したなら、ビルもろともの覚悟だった」
肝の据わった人である。
彼の辞書に「困難から逃げる」「自己保身」という言葉はない。
マクロンに所英樹の爪の垢を煎じて飲ませたいと思う所以だ。
初恋

シーンと静まり返った森のほとりに、ひっそりとたたずむ小さな沼。
平穏この上なき水面に、ぽちゃーんと石ころを投げ入れた衝撃が、波紋となってさわさわと広がっていく。
例えれば、初恋とはそんな感覚だろうか。
12月24日の今日、X(ツイッター)にはクリスマスの投稿があふれている。
その中に小学校1年生の女の子がケーキを食べている、とても可愛い投稿があった。
写真を見ていたらあの時のカナコちゃんが突如、脳裏によみがえってきた。
昭和40年代終わりの師走だった。
事の成り行きからして、24日か25日だったろう。
大学生の私は夕刊を配っていた。
日の短さに追われるがごとく、西の空は茜色からたちまち群青色に染まる。
和風の旧家と洋風の新築が混在し、ところどころに畑が残る昭和の新興住宅地を静かに夕闇が包み込んでいく。
絵に描いたような長閑で平和な風景だった。
練馬区を貫く新青梅街道から、2、3本入った裏通りの突き当りに岡本家はある。
その日は珍しいことに、門の外に1斗缶を持ち出して奥さんが焚火をしていた。
夕刊を手渡すと、私を呼び止める。
「お兄ちゃん、ちょっと待って!」
そして、今度は家に向かって大きな声で呼びかけた。
「カナコちゃーん、来たよー。速くしなさい!」
小学校1年生だろうか、女の子が門までは勢いよく駆けてきたが、お母さんの前で立ち止まりおずおずしている。
お母さんが促す。
「何しているのよ、早く渡しなさい」
カナコちゃんと呼ばれた女の子は俄かに笑顔をつくり、だが少し頬を赤らめながら、丸めて金色のリボンをかけたピンクの画用紙を私に差し出した。
お母さんが言う。
「この子が学校でつくった初めてのクリスマスカードよ。新聞屋さんなんかじゃなく、他に誰かいるでしょうと言ったけど、どうしても新聞配達のお兄ちゃんに渡すと言ってきかないの」
私は、ありがとうと言って受け取った。
「あなた、ラブレターをもらうなんて初めてでしょ。大事に取っておきなさいよ」
言い草には引っ掛かる部分も多いけれど、パリパリと小気味よいお母さんではある。
私は改めてカナコちゃんにお礼を言って、自転車をUターンさせた。
焚火に照らされた彼女は、まるでお人形さんのようにたたずみ私を見送ってくれた。
それにしても、ラブレターか。
もしかしたら、カナコちゃんの初恋ってことだろうか。
年末にこんな可愛いプレゼントをもらったら、もう1年分の嫌なことなどシベリアの彼方まで吹っ飛んでしまうのだ。
帰ってから二つ折りのクリスマスカードを開くと右側のページには私、左にはカナコちゃん。
二人と思われる似顔絵が描かれていた。
そして、なんとか読み取れる漢字で、岡本加奈子の署名も。
ああ、初恋!
誰もが一度は通る、はかなくも忘れ難き小径。
加奈子ちゃんは、どんな女性に成長しただろうか。
忘れられない神々しさと哀愁

なんと美しい栗毛だろう。
18歳の少年は栗毛の娘に一目惚れしてしまった。
少年は毎朝、顔を合わせるとポンポンと背中を二度叩いてやる。
それを合図に彼女は元気いっぱい朝の光へ駆け出していく。
夕方には愛おしい栗毛の頭を撫でてやるのが日課になっていた。
時には人目もはばからず思いっきり抱きしめてやることもあったけれど、周囲の大人たちはニコニコやさしく見守ってくれたのだった。
一年前にアメリカからやってきた彼女は、まばゆいほど健康的な四肢を伸び伸びさせて芝の上を時にはゆったり、時には疾走して一日を無邪気に楽しんだ。
無邪気ながらも頭のてっぺんからつま先まで、気品をまとった彼女の姿を見るたびに少年の胸はときめいた。
晩秋の日のことだった。
北海道にはいつ初雪が舞い降りても不思議のない季節だ。
けれど、その日は小春日和で、遠く澄み渡った西の空に雲がポツンと浮かんでいた。
牧場の片隅にたたずむ彼女は、その西の空を見つめている。
やわらかな日差しを浴びて栗毛はいつにも増して輝いていた。
はるかアメリカの故郷、テキサスへ思いをはせているのだろうか。
神々しい後ろ姿にどこか哀愁が見え隠れしていたのだった。

それから二ヶ月ほどして日高の牧場も一面雪に覆われたころ、突然、別れがやってきた。
永遠に続く出会いなどあるわけがない。
別れは世の常だ。
少年は牧場を去らなければならなかった。
大好きな彼女のもとを去ってまでも、追いかけなければならない夢があったのだ。
けれども、晩秋に見たあのワンシーンは永遠に少年の胸に刻まれた。
決して忘れることはないだろう。
彼女の名は『エクセレント』。
当時6歳のサラブレッドだった。
ゴム長の青春

着いたのは2月の上野駅だった。
前日、雪の札幌駅から特急列車に乗り、函館駅へ到着。
午後の青函連絡船で一路、青森港を目指したのだが津軽海峡の情景は何一つ覚えていない。
実はもう記憶さえとぎれとぎれの、はるか昔のことなのだ。
覚えているのは、札幌の倍近くもあろうかと思われた青森駅周辺の豪雪と東北本線の混雑だ。
上りの夜行列車は混沌と退屈と中途半端な眠気を乗せて長い闇をひた走る。
上野駅に降り立った時はすでに夜が明け切っていた。
改札を出て記念すべき内地での第一歩を踏み出したのだが、「ええっ、どうして?」と目を疑った。
真冬なのに雪がない。
しかもゴム長を履いているのは自分一人だ。
雪のない東京のど真ん中でたった一人ゴム長とは。
前年の3月に高校を卒業したばかりの19歳にとっては、顔から火が出る思いだった。
だが、今更どうしようもない。
恥を忍んで歩くより仕方なかった。
国鉄上野駅から少し歩いて、京成電鉄などを乗り継ぎ、最終目的地は千葉県の山奥だった。
どんな仕事が待っているのか、この時点では知らされていない。
というよりも、私を誘った連中も誰一人詳しく知らないのだから、のんきというべきか無鉄砲と言うべきなのか。
今思えばそんな無謀さえも、どうにかなった時代だったのだ。
私はどうしても大学へ行きたくて、お金を貯めようと郵便局を半年ほどで辞めてしまった。
もっと手っ取り早く稼ぎたいと思ったからだ。
当時、最も賃金の高い札幌の地下鉄工事現場で働いていたのだが、そこで知り合った連中から声をかけられたのだ。
「東京へ行くと日当2,500円もらえるぞ」
「よし、行く」
札幌冬季オリンピックを控えて、急ピッチで進む地下鉄工事は北海道でダントツの日当2,000円だったが、それより500円も高いという話に飛びついたのだ。
千葉県の五井駅に着くと迎えが来ていた。
車に揺られて20分も走っただろうか。
おんぼろ車は真新しい飯場の前で止まった。
真冬のプレハブ小屋から再スタートした仕事は、ゴルフ場予定地で樹木を伐採することだった。
もう、ゴム長も恥ずかしくなかった。
ひろみちゃんを必死に口説いた日

「写真のモデルを探しているんだ。お前の知っている女子学生で、一番美人だと思う女の子を紹介してくれよ。」
これは唐突過ぎて、困った相談だ。
頼んできたのは高校の同級生で、カメラマン志望の川埜だった。
彼とは高校卒業以来、親元を離れた東京で互いに助けたり、助けられたりしてきた無二の親友だ。
奴に頼まれたら、むげには断れない。
しばらく天井を仰いで「分かった」、というしかなかったのだ。
「浅草の三社祭を見物している自然なスナップを撮りたいから頼むよ。」
三社祭までもう2週間もないのに勝手に決め、奴は気軽に言い残して帰っていく。
こんな時、大概の男子学生は思うだろう。
「自分に美人の彼女がいたら、何も苦労しないのに」
私もその例にもれなかった。
美人どころか並の彼女もいないのだから、ない袖は振れないのである。
こうなったら、ターゲットを一人に絞って真正面から口説くしかない。
大学一の美人と言えば、真っ先に思い浮かぶのはひろみちゃんだ。
彼女ならアフリカの大草原で育った俊敏な青年でも、パリに生まれた青くさい御曹司でも、会った途端目を見張るに違いなかった。
同じ日本文学を専攻していたから授業では毎日のように会うし、立ち話しくらいなら気軽にできる仲だった。
だが、頼み事となれば話は別だ。
大学生になったばかりのコンパで悪酔いしてしまい、ちょっと彼女に絡んでしまったことがあった。
だから、私には良い印象を持っていないはずだ。
けれども、そんなことで躊躇している場合ではない。
いや、もう一つ問題があった。
彼女はいつも仲良し3人組で行動している。
中でもJ子は、ひろみちゃんの用心棒気取りであるから厄介だ。
口が悪くて、いつも男を敵視しているようなところがある。
あいつが、ひろみちゃんの傍を離れた隙を狙うしかない。
物事は思い悩むと、次々に問題点だけが頭に浮かんでくるものだ。
悩みなんて、どこかで見切らないと仕方ないのだ。
いつものように、あるところに行きついた。
「当たって砕けろ」
チャンスは意外に早くやってきた。
二日ほどした、午後だった。
珍しくひろみちゃんが、教室のドア近くに一人でぽつんと立っているではないか。
躊躇せずに近づいた。
「ひろみちゃんに、どうしても頼みたいことがある。明日一緒に昼食に行こう。
J子とNは連れてこないで」
拍子抜けするほど、あっさりOKしてくれた。
次の日は昼食もそこそこに、私は真正面から彼女に迫った。
あれほど真剣に女性を口説いたのは、もちろん初めてだ。
だが、彼女はなかなか落ちない。
「麻由美ちゃんの方が綺麗でしょ」
「藤尾さんなら喜んで引き受けんるんじゃない」
昭和の女の子らしい謙遜を繰り返しては、私を困らせる。
堂々巡りがしばらく続いたあと、私は鋭く決断を迫った。
「これは、ひろみちゃんじゃないとダメなんだよ」
「他には誰も考えていない。もし、ひろみちゃんに断られたら、この話を俺も友達に断るしかない」
彼女は口を閉じ、目を見開いて私をみつめた。
沈黙が続く。
それにしてもなんと、きれいな顔だ。
こんな娘を美人というのだろう。
透明感あふれる肌、キッと引き締まった口元、浮世絵師が引いた線のような鼻、大きく見開いた瞳、流麗な眉、どこを探しても欠点は見つからない。
こんな場面でも私は、見惚れてしまう。
すると彼女が口を開いた。
「で、いつなの?」
「あ、三社祭りを見物しながら写したいようだ」
「行ってみたいと思っていたけど、私、東京に来てから一度も三社祭に行ったことがないの。丁度よかった」
自分のためではなく、人のためという大義名分があれば人間は頑張れるものだ。
男と女

いつの頃からであろうか。
日本では『女性』と『男性』は善人で、『女』と『男』は悪人になってしまった。
新聞やテレビは、事件をこのように伝える。
「女はいきなり女性を刃物のような物で切りつけ、逃走した。女性は病院に搬送されたが意識はあり、命に別状はないという。警察は切りつけた女の行方を追っている」
加害者は女であり、被害者は女性と表記される。
これは男と男性の場合でも同じだ。
名前の確認が取れていないケースや本名を伏せたい時には使い分けができて、便利なのは確かだろう。
だが、ジェンダーフリーを声高に叫ぶメディアが、なぜ「性」を強調して善人とするのか、少し釈然としないものがある。
それはさておき、二つの言葉が持つ力の差は歴然としている。
メディアがこぞって女性を善人と奉っても、女の持つ深い味わいには決して勝てないのだ。
例えばモーパッサンの『女の一生』。
題名が『女の一生』だからこそ、どんな数奇な運命を辿ったのだろうと興味を引くが『女性の一生』なら、どこにでもある中流家庭に育った平凡な婦人の話かと勘違いされかねない。
現在に目を転じてもドラマのタイトルが『家売る女』だから、凄腕の女を連想してチャンネルを合わせる人は多いのだ。
これが『家売る女性』だったら、住み替えのため主婦が今住んでいる家を売りたいのか。
こんなのどこにでもある話だ、と見向きもされないだろう。
「男」という響きも、また凄いのだ。
『男性はつらいよ フーテンの寅次郎』では、48作のシリーズ化など夢のまた夢。
『男はつらいよ 寅次郎恋歌』だから、人情も情緒もほとばしるのだ。
『ラマンチャの男』だって同じだろう。
これが『ラマンチャの男性』なんてタイトルだったら、ロマンも何もあったものではない。
誰かの履歴書でも観せられるのかと思い、わざわざ映画館に足を運ぶ人などいるはずもないのだ。
箱根駅伝で駒澤大学の大八木監督が、「お前は、男だろ!」と檄を飛ばすから選手は奮い立つのだ。
これが「君は、男性だろ!」と呼びかけたなら、たちまち選手の脚はもつれ、沿道の観衆とテレビの視聴者は悪夢にうなされてしまうことだろう。
「ダバダ、ダバダバダ・・・・・」の音楽で有名なフランス映画だって、タイトルが『男性と女性』では、ホップもアルコールも入っていないビールのようなものだ。
やはり『男と女』でなければ、何も始まらないのだ。
「山のあなた」と「見果てぬ夢」

これまでいくつの詩を読んだことだろう。数々の作品に心動かされた一方で、多くの詩を忘れてしまった。
だが、生涯忘れることはないだろうと思うのが、カールブッセ作で上田敏の訳が秀逸な『山のあなた』だ。
山のあなたの 空遠く
「幸」住むと 人のいふ
噫、われひとゝ 尋めゆきて
涙さしぐみ かへりきぬ
山のあなたに なほ遠く
「幸」住むと 人のいふ
この詩と出会ったのは中学校の国語の教科書だった。
感動というよりは強い衝撃に襲われた記憶が残っている。
あの当時の私には「幸(さいわい)」の概念などまるでなかった。
山の彼方に求めていたのは、ただただ「夢」だけだった。
「いつか自分は、この田舎から遠くの町へ出ていくだろう。」その思いと「山のあなた」が重なった衝撃だったと思う。
だから、中学生の私には前半の二行しか頭に入ってこなかったのだ。
「自分の夢は山の彼方の空遠くにある」
夢破れた状況など、想像すらできない年齢だった。
あれから、もう何十年も夢を追い続けている。
捕まえた小さな夢もあるし、破れた夢は数知れない。今は、詩の後半二行が頭から離れない。
山のあなたに なお遠く
「幸」住むと 人のいふ
山の果てまで追いかけた夢に破れても、さらにもう一つの山の彼方へ思いをはせる。
憧れと真の幸せは違う。山の向こうに見える幸いは幻に過ぎない。
本当の幸せは身近な足元にある。
カールブッセや上田敏はそう伝えたかったのだと思う。
それでもなお、私は山の向こうに夢を見るのだ。
夢とチャンスは表裏一体だ。夢がなければチャンスもこない。
死ぬまで「見果てぬ夢」を追い続けることができたなら、これほど幸せな人生はないだろう。
バンコクの別れ

彼女は泣いていた。
大勢の人が行きかうタイ・バンコク郊外の国際空港ロビーだった。
はじめのうちは「ありがとう」と笑顔だったが、すぐに抑え難い感情に襲われた様子で、声をつまらせ両手で顔を覆う。
天真爛漫なほど明るかった彼女の涙を見ることになるなんて、想像もしていなかったので驚き戸惑った。
日本が高度経済成長路線をひた走っていた昭和49年の晩秋。
A新聞の奨学生だった私は4年間新聞配達を務め上げた褒美として、40人ほどの仲間とともにアジア旅行をプレゼントされた。
香港、シンガポールを経て最後の滞在地であるタイのバンコクで4日間を過ごし、移動には大型の貸切バスを使った。
関係者を含めた総勢40数人が2台に分乗するのだから、実にゆったりした旅行だ。
バスにはそれぞれ一人ずつガイドが付き、どちらもタイ人の夫を持つ日本女性だ。
別のバスを担当したガイドは、女優の倍賞美津子に似た個性的な美人だが、私たちの方はいたって平凡な顔立ちの日本女性だった。
だが、その平々凡々が明るくておしゃべりだから楽しい。
何よりも現地のことついて詳しいのには、誰もが感心し納得した。
豊富な話題にユーモアが加わり、バスの中はいつも笑いに包まれ和やかだった。
話はしばしば脱線するから、さらに盛り上がる。
「向こうのバスに乗っているガイドさんのご主人は、どうも秘密警察らしいの」
「家が隣同士なんだけど、私は一度も顔を見たことがないのよ」
座席から声が飛ぶ。
「そんなことバラしたら、秘密警察にならないじゃないか」
「大丈夫よ。あなたたちはもうすぐ日本に帰ってしまうし、当分はタイに来れないでしょうから」
SNSなどない、のんきでおおらかな時代だった。
見知らぬ異国の4日間で、ざっくばらんな彼女と我々学生たちの間には、サークルの先輩後輩のような雰囲気ができていた。
楽しかった旅行最後の日、バスは帰国便の待つ空港へ到着する。
彼女も一緒にバスを降りた。
空港ロビーに入ると誰からともなく「彼女を胴上げしようぜ」の声が上がる。
小柄な身体が二度三度宙に舞った。
「ありがとう。こんな楽しいガイドをしたのは初めて。あなたたちを見ていると、日本が急に恋しくなってしまって。私も帰りたくなって・・・・・」
もう最後の方は涙で声が震え、言葉にならない。
「こっちに来て間もなく結婚し、10数年間一度も日本に帰っていないの」と言っていた彼女の言葉を思い出した。
タイに来てから一度も帰国していないのはなぜだろう。
どんな理由があるのだろう。
一瞬だったが、私は彼女の身の上に想いを巡らせた。
だが、若かった自分に他人の事情など分かるはずもない。
間もなく彼女はいつもの明るさを取り戻した。
けれども頬に伝った涙を見て、彼女の人生の重さにちょっぴりだけ触れた思いがしたのだった。
かぐや姫はウイーンに行ってしまう

吉田由美子は不思議な少女だった。
私の学んだ大学は当時、入学試験に面接が必須の珍しい入試スタイルをとっていた。
一日目の学科試験が終わり二日目の面接日、教室で順番を待っていた時のことだ。
「どこの出身ですか」と隣の席から声をかけてきたのが、吉田由美子だった。
虚を突かれ「北海道」とぶっきらぼうに答えた。
「君はどこ?」と気の利いた問い返しなどできるはずもなく、私は読みかけの本に目を落とすのが精いっぱいだった。
だが、彼女は全く悪びれる気配がない。
自分は東京の江戸川区に住んでいると言い、それからも何度か話しかけてきたのだった。
待ちわびた大学生活が始まって1ヶ月が過ぎた五月の半ば、吉田由美子と再会した。
枝いっぱいに青い葉をつけたイチョウ並木が、キャンパスのど真ん中を貫いている。
その中央付近で、すれ違いざまにどちらからともなく「あっ」と声をあげ立ち止まった。
面接の順番を待つ間のぎこちない会話ながら、互いの名前と顔だけは忘れずにいたのだ。
私は一人だったが彼女の傍らにはボディーガードのように、男子学生二人が寄り添っている。
喫茶店に行き、雑談をしながら明日も四人で昼食をとる約束をして別れた。
「千葉君、明日も学校へ来るよね」。
それからは、四人で食事に行くと決まって吉田由美子はそう聞くのだが、私はその意図を間もなく察した。
二人のボディーガードは、どちらも彼女に好意を抱いている。
内山はあまりそのようなそぶりを見せないが、山形から出てきたという徳野はまるで遠慮がない。
「近い将来、必ず山形の田舎に由美ちゃんを連れて帰るぞ。
そして、両親や友人、親戚一同にこれが俺の彼女だと、大々的にお披露目するのだ」
口にこそ出さないがギラギラした顔に、ハッキリとそう書いてあるのだから正直な奴だ。
彼女にはそのことがよくわかるのだろう。
だから三人だけになることや二人きりになるのは、できる限り避けたかったのだ。
だが、三人といても私はあまり楽しくない。
新しい友人もできて、彼女たちとは次第に疎遠になっていった。
キャンパスのイチョウ並木があざやかな黄金色に染まった頃だった。
彼女は珍しく女友達と二人だけで歩いている。
ベンチに腰を掛けてしばらく話し込んだが、彼女の口から内山や徳野の名前が出ることはなかった。
学生の数が少なく小規模な大学だったから、それ以降も時々彼女の姿をキャンパス内で見かけるのだが、複数の男子学生に囲まれていることが多かった。
吉田由美子は、異性から本当に人気がある。
だが私には、その理由がよくわからない。
一緒に食事をしたり話す機会は何度もあったが、面接のときに向こうから声をかけてきたのがウソのようにおとなしい娘だった。
服装も地味で、見惚れるほどの美人でもない。
笑顔を絶やさず、黒髪からシャンプーの香りが漂ってくるような清潔感が特徴と言えただろうか。
2年生になると、そんな吉田由美子の姿を見る機会が、めっきりと減っていた。
特に夏休みが終わると全く出会うことがなくなったのだ。
もう彼女のことを忘れかけていたあくる年、2月の終わりだったと思う。
葉を落としたイチョウ並木が灰色の空の下で震えているような寒い午後だった。
校門をくぐると、暖かそうな紺色のコートに身を包んだ吉田由美子がこちらへ向かって歩いている。
「おお、しばらく。もう帰るの」
「あら、お久しぶり。なんだか懐かしいくらいお久しぶりね」
寒空の下、彼女の表情だけはもう春が来たように明るかった。
「今、退学届けを出してきたの」
「えっ、学校辞めたの?」
彼女は微笑を絶やさない。
「オーストリアへ留学するの。行くのはまだ先だけど、準備することがいっぱいあって」
「私には学問より、やっぱり音楽があっていると気づいたの」とも言った。
小学生のころから習っていたフルートを本格的に学ぶため、ウィーンに行くのだという。
都内の音大へ再入学することも考えたが、ウイーンで受け入れてくれる学校が見つかったので、そちらを優先したようだ。
昭和47年頃の話である。
私には到底理解の及ばない彼女の言葉だった。
貧しい北海道の漁村で育った私にとって、東京の大学で遭遇した1、2を争うカルチャーショックだった。
狐につままれたような思いで彼女の顔をみつめる。
しかし委細かまわず「元気でね」と言い残し、彼女は小さく手を振って歩き始めた。
未練など欠片もありません。
背中でそう表現しながら校門を出て行く。
右に曲がってすぐに姿は見えなくなった。
我が母校のかぐや姫は誰も手の届かないウィーンに行ってしまうのだ。
月に召されたかぐや姫のことが、この時とっさに私の脳裏をよぎった。
言い寄る数々の男たちになびくそぶりもみせず、はるか遠くに行ってしまうのは、かぐや姫も吉田由美子も同じではないか。
同時にあれほど男子学生に囲まれていた彼女の魅力に、その時ようやく気づいたのだ。
普段はつつましやかで控えめだけれど、内に秘めた意思の強さと物怖じしない大胆な行動力。
そのギャップが人を惹き付けて離さないのだろう。
もうすっかり忘れてしまっていた過去のことだったが、今秋のスーパーブルームーンを見ていたら、かぐや姫と重なって、なぜか19歳のまま彼女も月に映っているではないか。
月から迎えが来たときに「そのような所へ行くことも、嬉しいとも存じませぬ」。
かぐや姫は翁に、そのように言っている。
自分の意志とは裏腹に平安の都へ送られ、運命に逆らえず渋々月に帰らなければならなかったかぐや姫。
満月を見ると今頃どうしているのだろうかと、つい思ってしまう。
しかし、吉田由美子は違う。
どこに行こうが何をしようが、自分の意思を貫くのが彼女の生き方だった。
蒼い光に映し出された別れの日と同じ微笑みが、とても幸せそうに見えた。
かぐや姫にさえ、まさってしまう不思議な少女。
それが吉田由美子だ。
初めての観劇

小豆色の幕がスルスルと上がる。
舞台には出演者一同が正座し両手をつき、こうべを垂れて勢ぞろいしていた。
幕が上がり切ると最前列の真ん中に陣取る一人の女優だけが顏を上げ、口上を述べ始めた。
司葉子だ。
茹で卵のような色白の顔には不釣り合いなほど張りのある力強く、よく通る声だった。
ところがである。
隣にいた大村崑が突然顔をあげ、素っ頓狂な表情で意味不明な言葉を発しながら、彼女の口上を遮る。
客席を「ええっ?」と声にならない戸惑いが支配した。
若い私には何が起こったのかまるで理解できない。
「すっません」と関西弁の大村崑は、うなだれて元のようにこうべを垂れた。
司葉子が何事もなかったかの如く後を引きとり、口上の続きを述べる。
だが、あろうことか大村崑が再び支離滅裂なセリフをはさむからたまらない。
司葉子がキッと睨みつけ何か言葉を発した。
大村崑は萎れるように顔を伏せる。
司葉子の口上は続いたが、大村崑に三度目の異変が起きた。
顔をあげブツブツ何かつぶやきながら、例の鼻メガネでキョロキョロとあたりを見回している。
しかし、今度は客席のあちらこちらに笑いが起こった。
ようやく演出であることに気が付いたのだ。
笑い声とともに会場は安堵の雰囲気に包まれていく。
三度目で観客がやっと気づくほど、大村崑の演技は卓越していた。
不思議なものである。
こうしているうちに舞台と客席には一体感が生まれ、一挙にワクワク感が膨らむのだった。
私は完全に舞台での出来事に引き込まれていた。
演出家・花登筺の手法に苦も無くしてやられたのだ。
司葉子と大村崑の二人以外はこの間、じっとこうべを垂れたまま微動だにしないのだから、これまたすごいことではないか。
あの当時は気づかなかったが今ならわかる。
のっけから役者たちの何という名演技、プロ根性、そして花登筺の虚を突く見事な演出。
テレビでは新玉三千代のはまり役だった『細うで繁盛記』の女将を、私の観た舞台では司葉子が演じていた。
初めて観た本格的な舞台。
有楽町駅近くだと記憶しているが、劇場の名前すら忘れてしまった。
だが、劇の始まりは今も色あせることなく、脳裏に焼き付いている。
ジャニーズもAKBも誰一人出演していなかった、昭和四十年代終わりの舞台だった。
初めての観劇:木琴をたたく少女

司葉子と大村崑の絶妙な掛け合いで始まった初めて観る舞台『細うで繁盛記』に、いつの間にか私は夢中になっていた。
声を張り上げるようなセリフの言い回し、オーバーとも思えるゼスチャー。
いつも見ているテレビドラマのそれとは明らかに違っていた。
始めのうちは違和感を覚えたものだが、役者一人一人の巧みな演技にすっかり魅了されてしまったのだ。
涙あり、笑いありの舞台は、新鮮さと驚きを振りまきながら進行する。
劇が深刻な場面に変わったとき、渚に打ち寄せる波のように音楽が私の耳を襲った。
音につられて右に視線を移すと、通路を隔てた狭いスペースに楽団が並んでいるのに気づいた。
私は、舞台にかなり近い席の最も通路側に陣取っている。
舞台の袖付近から通路に沿って弦楽器、管楽器、打楽器が入り混じって一列に並び、一番端っこに木琴の奏者がいた。
私の席の真横だったが、木琴を打つ手に思わず目を見張った。
バチを持つ両手は華奢だが、動きは実に素速くリズミカルだ。
時にはやさしく、時には甲高く、そして時には転がるようなリズムで胸に迫って来る。
こんなに多彩できれいな木琴の音色を聞くのは、はじめてだった。
手の動きに見惚れ、奏でる音に聞き惚れてしまった。
彼女が手を休めて顔をあげる。
「えっ」、今度は顏に見惚れてしまう。
クリクリッと大きな黒く輝く瞳が、何とも印象的だった。
互いに手を伸ばせば届くのではないかと思うほどの距離だから、じっとみつめる私と視線が合う。
彼女は戸惑い、はにかんでいる。
咲いたばかりのタンポポが、春のそよ風に揺れるがごとく可憐な、あの表情を今でも忘れられない。
しかし、彼女ばかりを見てはいられない。
クライマックスを迎えつつある劇も気になる。
舞台に注目し、木琴の少女に目移りしながら、初めての観劇は俄かに忙しくなったのだった。
当時、20歳を過ぎたばかりの私よりさらに若く見えた彼女。
もし、本当に10代の少女だったら、天才だろう。
昭和40年代とはいえ、あのように本格的な舞台の楽団員を10代の少女が務めるなんて、冷静に考えたら無理がある。
私の大いなる勘違いだったのかもしれない。
だが、思い出なんてたわいないもの。
思い出の中の彼女は、永遠に少女でいい。
覚悟の告白

彼女は高校卒業まで北海道の函館で育った。
市内髄一の名門高校から東京の超難関私大へ進み、有名企業へ就職したが数年で職を辞し、絵画モデルになった。
横浜在住の彼女から突如LINE電話が入ったのは、2023年7月のことだった。
電話の彼女は落ち着いている。
きれいな日本語とよく通る声で淡々と話した。
「ずっと考えていたのですが、司法試験に挑戦することに決めました」
「司法試験?法律を学んだことがあるの?」
「大学は法学部だったので、それなりに法律の勉強はしています」
その後、話は急展開する。
「私は虐待されて育ちました」
幼少から現在まで、彼女はさぞかし順風満帆に過ごしてきたのだろうと勝手に想像していたが、その一言に思わず絶句した。
決して感情を高ぶらせることなく過酷だった子ども時代の家庭環境を、淡々と話す彼女の一言ひと言が私の胸に突き刺さる。
あの素直な横顔に信じがたい過去が隠されていたなんて、だれが想像できよう。
「だから、恋愛をしてもうまくいかないのです」
この言葉に若い彼女の苦悩が凝縮されている。
彼女との出会いは2020年3月だった。
東京で開催されたセミナーに出席したとき、たまたま昼食のテーブルで一緒になったのだ。
同席した4人はすぐに打ち解け、ごく自然にLINE交換することになった。
その後、コロナが猛威を振るう中で、LINEでのやり取りは細々と続いていた。
電話で聞く限り、売れっ子絵画モデルとなった彼女の収入はかなりのものらしい。
金銭的には何一つ不自由ない生活を送っているのだから、自分を苦しめた家族と絶縁状態になるのは当然の成り行きだろう。
だが、無性に誰かと話したい思いに駆られるのが人間だ。
密かに胸にしまっておいた思いを吐露したい。
自分の存在を人生を誰かに認めてもらいたい。
そして、自分の決意を語る相手が欲しい。
そんな欲求は人としてごく自然なことだろう。
恋愛がうまくいかないから恋人はいない。
だから辛かった過去と決別し、新たな未来への挑戦を聞いてもらうために、彼女が歳も距離も遠く離れた私を選んだのは不思議でも何でもない。
若き彼女にとって、覚悟の告白だといえよう。
強い決意がにじむ彼女の言葉を肯定することが私の役目だと思い、惜しみない励ましの言葉を贈った。
今はただ、彼女が選択した狭き門の突破を静かに願うばかりだ。
何年かかるだろうか。
長い道のりになるだろうけれど、彼女の挑戦に心から拍手を送りたい。
なお、この記事にはプライバシーの保護上、ほんの少しだけ脚色を加えていることをご承知ください。
ビックリ仰天!彼女の過去

「Mさん、どうぞ先に打ってください」
「え、先に打っていいですか?」
そう言って彼女は、白いマークのレギュラーティーでアドレスをとった。
シュッと一度だけ素振りをして、パッシーンと小気味よく打っていく。
白球は晴れ渡った青い空に弧を描いた後、緑のフェアウェイを200ヤード近くまで転がる。
50ヤードほど前方にあるレディースティを使用するだろうと思い、先に打ってくださいと気をつかったつもりだったけれど、まったく余計なお世話だった。
並の男と遜色のない飛距離だ。
思わず「ナイスショット!」と声を張り上げたが、この時はまだ彼女の「えっ!」と驚く過去など知る由もなかった。
この日、私はゴルフコンペに参加していた。
場所は栃木県のプレステージカントリークラブ。
男子プロのトーナメントが何度も開催されたチャンピオンコースだ。
時は平成元年10月下旬。
芝生はまだ青々としているし、早朝なら涼を通り越して肌寒ささえ感じる、最高のゴルフシーズンだ。
彼女は会場のプレステージCCを所有し、コンペを主催した会社の常務取締役だった。
私より少し若い30代半ばだろうか。
並の美形ではない。
172㎝の私と並んでも遜色のないスラリとした長身のシルエットが緑の芝生によく映えた。
動作は実にテキパキとしていたが、最も印象に残っているのは姿勢の良さだ。
背筋がピーンと伸び、立ち居振る舞いはまるでランウエーを行くファッションモデルを彷彿させた。
ハーフラウンドを終えて昼食のテーブルに着く。
彼女のコンシェルジュぶりが、これまた素晴らしい。
レストランのことは隅々まで把握している。
案内はコース設計者から豪華絢爛なクラブハウスの構造にまで及んだ。
見事な見識と博識と言えよう。
この日のもう一人の同伴者は、あるゴルフ業界団体の事務局長だった。
弁舌さわやかでジョーク好きの愛すべき男だ。
その彼が圧倒されたのか、ほぼ口を開かないほど彼女のトークが素晴らしかったのだ。
決してしゃべり過ぎの印象は与えないし、こちらの質問にも的確に答える。
才色兼備を絵に描いたような女性だ。
彼女はゴルフ業界では知る人ぞ知る存在だった。
有名航空会社のスチュワーデス(当時はそう呼んでいた)から、ゴルフ場の支配人に転身した異色の経歴が話題になり、メディアによく登場した。
そして、間もなく別のゴルフ場運営会社にヘッドハンティングされる。
移籍した会社で常務に抜擢されたのだ。
だから私は彼女を知っていたが、対面するのは初めてだった。
このコンペをきっかけに、彼女の会社からパーティーやイベントの案内状が時々届くようになる。
パーティーでは二人並んでワイングラスを傾けることもあったが、話題はいつも仕事関係ばかりだ。
やがてバブル経済が崩壊し、疎遠になった。
平成10年前後には、彼女の会社が倒産したことをニュースで知る。
さらに時は流れ、平成20年ころのことだったと思う。
事務所に不動産会社の営業マンK君が訪ねてきた。
その日は雑談に花が咲き、彼がM女史の部下だったことを知った。
「Mさんには、とてもお世話になったものです」
そして、彼は予想もしなかったことを口にした。
「あの方は、ミスユニバースの日本代表でした」
一緒に懇談していた若い社員が、すぐにネットを検索する。
良家の御曹司や令嬢が通うことで有名な大学の在学中に、日本代表としてプエルトリコで開催されたミスユニバース世界大会に出場していたのだった。
なんと、ビックリ仰天の過去ではないか。
年齢も私と同じだった。
あの、美しい姿勢とシルエット、そして一つひとつのしぐさが昨日のことのように脳裏によみがえる。
「なるほど、ミスユニバース日本代表か。どおりで」と、一人合点がいったのだった。
寂寥

初夏の穏やかな日だった。
目の前には群青色の小樽港がたたずみ、防波堤を超えたその先には青く澄んだ石狩湾が洋々と横たわっている。
キラキラと午後の光が水面に踊り、この日は港も海もまぶしいほど輝いていた。
私は小樽港勝納ふ頭の端にある、フェリーターミナルの二階レストランで遅い昼食をとっていた。
広い店内には他に誰もいない。
窓の右手には否が応でも目に入る、巨大な船が停泊している。
勝納ふ頭に突如、白い丘が出現したのかと思わせるほど大きい。
だが、そのたたずまいを支配するのは、気品と優雅と絢爛だ。
豪華客船ダイヤモンドプリンセスだった。
船は、もうすぐ出港するらしい。
デッキから身を乗り出すように手を振る乗客が何人も見える。
一組のテーブルと椅子が置かれたターミナルの小さな庭園に降り、私は腰を掛けてダイヤモンドプリンセスを眺めた。
ふ頭にはフラダンスを踊って見送る女性数人の姿があり、その傍らでカメラを構える人、手を振って乗客に応える若い母親と幼い子、身を寄せ合って談笑するカップル、忙しく動き回る関係者など、陸の人間模様は様々だ。
間もなく船上から五色のテープが十本ほど投げられ、「ジャーン、ジャーン」と銅鑼が鳴る。
次の瞬間だった。
天地の間を震わせ「ブオーッ!」と汽笛が響く。
その、たった一度の切ない叫びが、私の五感を揺さぶった。
突如として得体のしれない感情に襲われたのだった。
家族はおろか、友人も知人も誰一人乗っているわけではないのに、全身を突き抜けていく寂寥。
いつの間にか立ち上がり、動き出した船に近づいていた。
出船は別れだ。
見知らぬ人たちを乗せた船が遠ざかって行くのも、また別れに違いない。
私は降って湧いた感傷に、しばし身を任せるしかなかった。
ダイヤモンドプリンセスは港の中央で大きく旋回し、赤灯台と白灯台の間をゆっくりと通り抜け外洋へ出た。
船尾から噴き出すように白い波が渦巻くと、速度を増し船影は次第に北へ遠ざかる。
パンデミックが世間を震撼させる少し前のことだった。
港町小樽の忘れ得ぬ一日に黄昏が迫っていた。
空の上の仕事人

「こいつとこれから、7時間も一緒とは」
私はホノルル行きのJAL機内で、うんざりしていた。
ついさっきまでは、初めて座ったファーストクラスで心浮き浮きだったのに。
成田空港で機内へ案内されると隣の席には、まだ誰もいない。
「この席に座るのは、もしかしてダイアン・レインのような・・・」と想像をたくましくしていたのだった。
だが、出発間際に現れた男によって、妄想はしぼむどころか音を立てて破裂した。
男は座席の横に立つと乱暴に靴を脱ぎ、勢い余って片方がゴロンとひっくり返る。
それには目もくれず上着を床に脱ぎ捨て、外したネクタイを放り投げるではないか。
スチュワーデス(客室乗務員)がやって来て、表情一つ変えず手慣れた様子で目の前の収納スペースへ片づける。
飛行機は間もなく飛び立った。
離陸して1時間ほど経っただろうか、食事が運ばれてきた。
隣りの男がまじまじとのぞき込む。
「何?その弁当は。こっちとは違うな」
「ああ、私は肉を食べないから」
通路と座席を仕切っているカーテンが開いて、顔をのぞかせたのは男性のチーフパーサーだった。
「C様のような肉を召し上がらない方も、欧米では菜食主義になります。私は20年以上飛行機に乗っていますが、菜食主義のお客様は、日本人より欧米人のほうが多いですね」
場を和ませようとスチュワーデスもパーサーも、いろいろ気を使ってくれるのだったが、鈍感な奴には人の気遣いなどわかるはずもない。
「何しにハワイに行くの」
今度はそう聞いてくる。
仕方なく答える。
「社員を連れて、慰安旅行」
「ハワイまで行って、ただ遊ぶだけではもったいない。不動産を買っておけば、今なら黙っていても儲かる。私がいい物件を紹介するよ」
そう言いながら、怪しげな社名の入った名刺を出した。
実に鬱陶しい。
教養のかけらも感じさせない不思議な男だった。
現在のファーストクラスは個室が主流だ。
けれども、バブル経済華やかなりし頃の1989年当時は、多くがペア席だった。
地上を遠く離れた空の上で、こんな奴とペアを組むことになるなんて、ああ世間とは本当にままならないものだ。
これはもう、観念してタヌキ寝入りを決め込むより他ない。
目をつぶってしばらくすると隣の席から人の立ち上がる気配がした。
その、わずか数秒後だった。
座席横のカーテンがサッと開く。
「C様、どうぞこちらへ。そのままでどうぞ。
靴もお荷物も後で私が運びますから」
私はスチュワーデスに手を引かれるように、スリッパのまま別の席へ移った。
その席は二つとも空いている。
リクライニングシートを少しだけ倒してゆったり身を沈めた。
そして、席を確保し荷物を片づけてくれた彼女に謝意を伝えながら、グラスワインを頼んだ。
すぐにチーフパーサーもやって来て、静かな声で言う。
「こちらで、どうぞごゆっくりおくつろぎください」
なんという素早い動き。
しかも誰をも傷つけないように、敵が席から消えたわずかな時間を狙ったのだ。
息の合った二人の連携。
これぞプロの仕事だ。
隣の男に「あいつはどうした?」と聞かれた彼女が
「あのお客様は、銀河鉄道にお乗り換えになられました」。
そう答えたら実に愉快なのに、などと考えているうちに本当の眠気が襲ってきた。
おばさん構文とマルハラ

産経新聞のインターネットニュースによると、末尾に『。』を付けて送るLINEの文章を「マルハラ」というらしい。
「分かりました。」「連絡ください。」などの『。』に恐怖心を抱くのだという。
誰が恐怖するのかと思ったら、どうやら若者らしい。
若者と言っても、主に中高校生や大学生のようだが。
では、どうすればよいのか。
若者の SNS利用に詳しいというITジャーナリストを名乗る大学の客員教授は、文末に絵文字や『!』を多用すべきだと産経新聞に答えている。
しかし、LINEで絵文字を多用するのは「おじさん、おばさん構文」だという記事を見たばかりなんだけどなあ。
それと『!』の多用ですか。
「わかったわよ!」、私には、こっちの方が怒られているようで怖い。
昨日『絵文字の多用はおじさん構文』の記事を読み、今日は『LINEの句点はおばさん構文』のニュースを見る。
世間はかなり混乱しているらしい。
麻生太郎さんが上川外務大臣を「おばさん」呼ばわりすれば世をあげてバッシングなのに、庶民レベルでは「おばさん構文」「おじさん構文」の応酬と揶揄で盛り上がる。
それにしてもマルハラとは。
日本が世界に誇る文字文化の定型通りに書いてハラスメントとは、あまりにも短絡で情けない。
メデアが面白おかしく取り上げ、その周辺でうろつくコバンザメのような人々が無分別に騒ぎ立てる社会こそ心配だ。
そんなことを考えながら、少し複雑な心境でX(Twitter)を眺めていると、俵万智さんのこんな歌に出会った。
句点を打つのも、おばさん構文と聞いて…この一首をそっと置いておきますね〜
『優しさにひとつ気がつく ✕でなく○で必ず終わる日本語』
やっぱり本物は違う。
この投稿には「イイネ」が3万5千以上もついている。
分かる人は、まだまだたくさんいるのだ。
安心しましたよ!
厨房男子の造った三升漬

高校時時代の同級生10数人で会話をするLINEグループがある。
昨年12月の半ばだった。
そのLINE上で私を名指しして「市販品の三升漬を食べたことがあるか?」と、横浜在住の西島滋夫君が聞いてきた。
「三升漬?」
さて、名前は聞いたことがあるような、ないような。
だが、食べた記憶は全くない。
「三升漬は食べたことがない」と返す。
西島君は「ネット通販で三升漬を取り寄せたが、昔、母がつくっていたものとはコクも辛さも全く違う」と訴えるのだ。
そのやり取りを見て、札幌の高橋守君が珍しく会話に参加する。
「俺のつくった三升漬が少し残っているからあげるよ。」
それから1週間ほどして札幌の手稲駅近くで会い、小瓶に入った高橋君手造りの三升漬をもらった。
醤油、麴、青唐辛子をそれぞれ1升ずつ混ぜ合わせて漬けることから、三升漬の名がついたのだという。
東北、北海道では保存食の定番らしい。
子どもの頃、私の実家でも多くの保存食を作っていた。
何種類かの漬物は勿論のこと、父が漁師だったから飯寿司はお手の物だった。
だが、三升漬はつくったことがない。
三升漬をもらった日の夕食は、鱈チリにした。
鱈の切り身と木綿豆腐だけを鍋に放り込みポン酢で食べるのだから、実にシンプルだ。
いつものポン酢に、箸で一つかみ三升漬を入れる。
北海道でいうところの青南蛮が、シャキシャキと歯応え十分だ。
噛んでから、やや間をおいてじわじわと辛さが口に広がる。
辛さに隠れるような控え目の酸味は麴だろうか。
三升漬のコクが味の薄い鱈と豆腐の存在を引き立てるから、これぞまさしく名わき役の隠し味だ。
次の日は、カレーに入れてみた。
私は肉を食べないから、我が家のカレーには肉類が一切入らない。
だから、どうしても出汁とコクが一味不足する。
ところが三升漬を入れると、いやーこれはもう素晴らしいコクのあるカレーに仕上がるからびっくりだ。
青南蛮が入っているので、辛さも増す。
高橋君からもらった小瓶が空になるころ、今度は西島君からやはり手造りの三升漬が届いた。
市販品では満足できず、子どもの頃に母がつくっていたのを見よう見まねで再現したのだという。
こちらは、青南蛮の切り方が大きいから辛みが一層強い。
噛んだ後しばらくは、口いっぱいの辛さが続く。
冷奴、湯豆腐など豆腐料理との相性が抜群だし、野菜炒めやピリ辛エビマヨなども最高だ。
料理に少し入れるだけで芳醇さがグッと増すから、三升漬は実に優れた調味料だ。
ちなみに、高橋君の実家は割烹料理店で、跡を継いだお兄さんが天婦羅店に改装。
その天婦羅の味は、岩内町でも評判になるほどだった。
また西島君の実家は、共和町でも指折りの農家だった。
今では全国的なブランドとなった、雷電メロンを早くから生産していたのだが、厳冬を超す北海道の農家だから保存食は造って当たり前。
二人とも、血は争えないというか、蛙の子は蛙というべきか、はたまた「門前の小僧、習わぬ経を読む」とでも例えるべきか。
元々、食造りの才はあったのだろう。
そうこうしているうちに青南蛮が手に入ったので、次の三升漬を仕込んだと西島君から連絡がきた。
厨房男子二人がつくる三升漬のおかげで、今夜も酒が旨い。
まだ見ぬ女(ひと)

私はサラブレッドが大好きで若い頃、半年ほど牧場で働いたことがある。
広々とした牧草地でのんびりと草をはむ姿は優雅で、見ているこっちの心まで和むのだ。
時には、鬣をなびかせ十数頭が一斉に小高い丘を駆け巡る姿の、何と壮麗なことか。
サラブレッドと共に過ごした牧場の得難い日々は、今も薄れることなく脳裏に焼き付いたままだ。
だから私は、まだ見ぬ女(ひと)を想うとき、その姿を牧場に絡めてイメージしてしまう。
手綱を自在に操り、青々と深い芝生の上を東に西にと駆け巡る小麦色した少女。
麦わら帽子を目深ににかぶり、長い首に赤いハンカチーフを巻いて馬上に揺れながら、風の中を颯爽と近づいてくる優美な女(ひと)。
或はまた、黒いツーピースに身を包み、厩舎前に停まった高級車の後部座席から、妖しい笑みをたたえて降り立つ貴婦人。
などなど、いろんな姿が浮かんでくるのだ。
彼女は、一体どんなタイプだろう。
朝野ゆかりさんとはインターネットで知り合って、もう1年ほど経つだろうか。
律義な人で、四季折々にメールを通じてカードを贈ってくれる。
季節を表現する写真や図柄から、センスとやさしさがしのばれるのだ。
そんなカードを見ながら、私は牧場と彼女を重ねる。
しかし、朝野ゆかりさんに関する情報はごくわずかだ。
長崎出身であること、女優の石田ゆり子似であること、律義でやさしい性格であることくらいしか知らない。
だが、たまに送られてくるメールに目を通しながら、もう何年も前からの知り合いであるような錯覚に陥ることもある。
彼女には、人をそう思わせる何かがある。
だが、具体的に問われれば、それが何かはまだ分からない。
人は完成したものより未完のもの、中断された出来事により興味を持つという。
心理学で言う、ザイガニック効果というヤツだ。
テレビドラマや映画の予告編は、この効果を狙って作成される。
断片的な映像や音声は視聴者の想像力を掻き立て、より強く印象に残るからだ。
このように情報が少なければ少ないなりに、人は想像を膨らませるものだ。
メールやカードが送られてくるたびに、永遠に未完な朝野ゆかりさんのイメージを私はこれからも組み立て続けるだろう。
颯爽と麦わら帽子の粋な女か、はたまた高級車に乗った妖しい笑みの貴婦人か。
少女でないことだけは確かだろう。
『山線』に乗ってみたい!

「そうですね、そんな時間ができたら”山線”に乗ってみたいですね」。
ちょっとはにかみながらも明るい表情で、そう言ったのは将棋の藤井聡太八冠だ。
小樽の銀鱗荘で『竜王』の防衛戦第4局が行われ、4連勝で初防衛を果たした翌日の記者会見でのことだった。
「小樽から好きな場所へ自由に行っていいとしたら、どこへ行ってみたい?」との質問が飛ぶ。
それに対する答えが「山線に乗りたい」だった。
JR函館本線の一部である小樽~長万部間の単線を通称『山線』という。
1時間に1本ほどのダイヤで、1両または2両のディーゼルカーが後志の山間部をのんびり走っている。
それにしても鉄道に乗ることが趣味とは言え、愛知県出身の藤井さんから山線の名を聞くとは驚きだ。
おそらく、対局会場となる地方の土地柄や特徴を事前に調べるのが彼の習慣なのだろう。
惜しみない努力と、対局する地元への配慮が垣間見えるエピソードだ。
ただの天才ではない。
配慮を忘れない魅力たっぷりの若者だ。
そしてもう一つ、山線に乗ってみたいという言葉の裏に「静かな、のんびりした時間が欲しい」との願望も見え隠れする。
北海道新幹線の札幌延伸と引き換えに、このローカル線は廃止が決まっている。
昭和の風物詩が、また一つ消えるのだ。
静かでのんびりした毎日を送っている私だが、藤井さんの話を聞いて廃線前に、小樽~長万部間を往復してみたくなった。
少年時代、何度も乗った懐かしい山線。
雪景色もいいが、白樺の梢が萌え、山桜の咲くころが最高だ。
ババ自慢

示唆に富んだ祖母の一言に、これまでどれほど励まされたことだろう。
明治生まれの祖母は実に多才な人だった。
料理の味は天下一品で、正月や学校行事に用意してくれるお重の盛つけが、いつも目を見張るほど色鮮やかだった。
天性の色彩感覚と言っていいだろう。
裁縫は近隣の娘たちが習いにきたほどの腕前だった。
しかも、自分は誰から習ったわけではなく、古い着物をほごしながら仕立て方を覚えたのだという。
明治時代、まだ未開だった北海道の辺境で育ち学校とは無縁なのに字を読めたし、畑仕事も玄人はだしだった。
猫の額のような土地を耕して花を植え、トウキビ、イチゴ、スイカ、アジウリなどを栽培する。
昭和30年代後半には、メロン栽培に成功し周囲を驚かせた。
お陰で私たち孫は、毎年のように季節の味覚を堪能できたのだ。
今でも慶弔事に親戚一同が集まると、必ずと言っていいほど祖母の話題が出る。
孫が競うように偉大さを称えるのだ。
それを聞きながら兄嫁が笑う。
「始まりました。ババ自慢」
祖母の凄さはそれにとどまらない。
小学生の時に聞いた言葉があまりにも哲学的だ。
9月の半ばだったと思う。
北海道は秋の長雨に見舞われていた。
「イヤだなあ、この雨。いつになったら晴れるんだろう」
毎日、毎日降り続く雨が道端の泥をはね上げるのを見て、憂鬱を超え心細ささえ覚えた小学生の私がポツリと漏らしたのだ。
それに対して笑いながら発した祖母の一言に、心が少し軽くなった記憶が残っている。
だが幼い私は、その場限りですぐに忘れてしまっていた。
あの時の至言が忽然と頭に浮かんだのは、経営していた会社が苦境にあえいでいた時のことだった。
「心配ないよ。今まで止まない雨は降ったことがないから」
それ以来、この言葉に励まされたことは一度や二度ではない。
大人になってようやく、言葉の持つ意味の重さが分かったのだった。
今は「止まない雨はない」が流布しているけれどメデアが限られていたあの頃は、まだ一般的な言葉ではなかったはずだ。
いつも前向きで愚痴など一度もこぼしたことのない天才ババは、私の中に今もしっかりと生きている。
潮太鼓と男たちの望郷

おたる潮まつりに欠かせないのが『潮太鼓』だ。
潮ねりこみが祭りの華なら、潮太鼓は怒涛だ。
はるか水平線から迫り来る豊饒の海、日本海を見事なバチさばきで再現する。
その立ち上がりは穏やかな凪。
ドーン、ドーンと音の波は次第に強く、雄々しく地響きのように押し寄せ、やがて天も裂けよとばかりに周囲を圧倒する。
聞きほれている間は邪念さえ吹き飛んでしまう。
怒涛が海を浄化するがごとく、潮太鼓は心を洗い流して静かに引いていく。
『おたる潮まつり50回記念誌』によると、潮太鼓は石川県がルーツとされている。
潮まつりの前身ともいうべき『みなと小樽商工観光まつり』が開催されていた昭和三十年代の事だった。
本格的な太鼓隊を編成して、祭りをもっと盛り上げたいと考えていた商工会議所の役員がある晩、竜宮神社を訪れる。
社殿から聴こえてきたのは、太鼓の音だった。
トトトーン、トントン、ドドドーン、ドンドン。
リズミカルだが満月の夜空に届けとばかりの迫力があった。
音色は閃光のように役員のつま先から、脳天までを貫いていく。
役員はすっかりほれ込んでしまった。
太鼓を打っているのは、ねじり鉢巻の男三人だった。
ほろ酔い加減も加わり顔が紅潮し、なんと気持ちよさそうな表情だろう。
三人は石川県から出稼ぎに来て、小樽に居ついたのだった。
彼らが生まれた漁村に、古くから伝わる打ち方なのだという。
役員は、すぐさま伝統の技を小樽の若者に伝授するよう頼み込む。
彼らは快く引き受ける。
潮太鼓が芽吹いた瞬間だった。
時は過ぎ、昭和42年の夏、第一回『おたる潮まつり』が開催される。
関係者たちの思いと努力が実を結び、これを機に『潮太鼓保存会』が結成されたのだった。

明治から戦前にかけてニシン漁に沸いた小樽の忍路や祝津には、北陸地方から大勢の男たちが出稼ぎにやって来た。
ヤン衆と呼ばれる人々だ。
彼らが故郷に思いをはせて叩いていた太鼓こそが、潮太鼓のルーツだった。
時には自分を育んだ忘れ難き故郷の山河を思い、ある者は胸にしまい込んだ忘れ得ぬ人の面影をしのびつつ、目頭を熱くしながらバチを打ち続けたのだろう。
はるばる石川県の漁村から運ばれた潮太鼓の種子は、こうして北前船の時代から密かに芽吹くチャンスを待っていたのだった。
ヤン衆の中には、自らの意志で小樽に残った人々がいる。
一方で故郷へ帰りたかったけれど、諸々の事情を抱えて願いが叶わなかった者も多くいたことだろう。
叶わぬ帰郷。
潮太鼓を聞くたびに、そんな男たちの望郷が私の胸をゆするのだ。
例年、多くの子どもたちが参加する潮まつりは、夏休みが始まったばかりの七月最終週の金・土・日に行われる。
先人たちの想いを知ってか知らずか、大人たちに混じって潮太鼓を打つ子どもたちの目は真剣そのものだ。
阿吽

平成2年7月初旬の日曜日、私は小金井カントリー俱楽部のレストランにいた。
ゴルフ会員権が日本で一番高いことで有名なゴルフ場だ。
この日、一緒にプレーした四人のうち、貸しビル業を営むオーナー社長だけが倶楽部の会員だった。
一人は中堅証券会社の社長で、もう一人は生命保険会社の常務だ。
4人の中で唯一30代だった私は、どう見たってはなたれ小僧に過ぎない。
東京は梅雨の真っ只中にあり、この日も前日からの雨が降り続いていた。
雨のゴルフはつまらない。
苦痛ばかりで、大自然相手の解放感や爽快感がまるでない。
何とか前半のハーフラウンドを終えて、昼食のテーブルに着いたばかりだった。
例によってビールで乾杯する。
「どうだい千葉さん、午後もやるかい?」
会員の社長が、出身地の北海道訛りを交えながら言う。
若輩の私に後半のハーフランドをプレーするかしないかを決める権限などあるわけがない。
「雨がやみそうもないから、やめましょう」の言葉を期待しての問いかけだった。
この社長特有の言い回しだ。
次のセリフも予想通りだった。
「一番若くて元気な千葉さんがやめようと言ってるから、止め、止め」
決して大雨とは言えない状況だった。
しかも日本を代表する伝統の名門だ。
会員はいつでも来れるが、ビジターはそう簡単にプレーできない格式の高いゴルフ場だった。
ワンマン社長といえども、それなりの地位にあるビジター二人には気を使わなければならない。
ハーフラウンドで切り上げるのは勇気がいるのだ。
ここで私が
「この程度の雨ですから、あとハーフ行きましょう」
などと言ったら、社長が頭に描くシナリオは成立しない。
私はこの手のタイプには慣れているし、二人のお偉いさんとは特に利害関係がないからワンマン親爺の気持ちを斟酌するには何の抵抗もなかったのだ。
名門ゴルフ場はまた、社交場の顔を持っている。
レストランでの和気あいあいとした小宴会は大歓迎されるのだ。
真昼間から、4人で高級ワインを5本も空けた記憶が残っている。
社長の描いたシナリオ通りに演じた私には、ワインを遠慮なく空ける権利があったのだ。
プレー代も含めた4人すべての勘定は、気分を良くしたワンマン社長のおごりになった。
阿吽の呼吸。
これもまた、日本の古き良き伝統だろう。
時は、バブル経済の絶頂期にあった。
小樽潮まつりの「ねりこみ」を完成させた、たった一言の威力

小樽市立図書館の二階に案内され、係の人が施錠された部屋から分厚い本を持ってきてくれた。
「貸し出しはできませんので、こちらで読んでください」。
表題が「おたる潮まつり50回記念誌」だったと記憶している。
ブログに書こうと思い、『潮まつり』について調べていた時のことだった。
祭りが企画された経緯から『潮音頭』の作詞・作曲について、さらには三波春夫のレコーディングにこぎつけるまでの苦労話やエピソードがドラマチックに描かれている。
目を奪われたのは『ねりこみ』についての記述だった。
『ねりこみ』とは、潮まつりで踊る振り付けのことだ。
国民的歌手の三波春夫が歌ったレコードも出来上がり、踊りの振り付けだけが残されていた。
祭りの実行委員会は、日本舞踊の各流派に共同で『ねりこみ』を創作するよう依頼する。
一つの流派だけを指名すれば、他流派の反発は必至だ。
後々、しこりが残らないように苦肉の策だった。
気位の高い小樽花柳界に対しては、危惧があった。
北海道一の商業都市を謳歌した頃の小樽には、500人もの芸者がいたという。
その芸者をはじめ、飛ぶ鳥を落とす勢いを誇った大富豪の夫人やお嬢様たちを弟子に抱えていたのだから、師匠たちのプライドたるや想像を絶するものだった。
流派は同じでも師匠が違えば、弟子たちは口を利くのも許されない異様な世界だったと伝えられている。
これでは短期間で一つにまとまるのは至難の技だろう。
誰もがそう危惧したのだ。
日程はすでに決まっていて、祭り開催までの時間は迫っている。
関係者の不安は募った。
花柳流、藤間流、創作舞踊など各派が勢ぞろいした第一回目の会合は、そうした波乱含みの中で開催された。
会場に重い空気が流れる。
流れに逆らい、静かだが凛とした声が響く。
「小樽のためなら、どんなことでも協力しなさい。お世話になった小樽に恩返しするために、命も投げ出すつもりでやり遂げなさい」
臨席していた最古参の師匠が愛弟子たちに放った一言は、瞬時に場の雰囲気を変えたのだ。
素晴らしい威力だった。
一芸を極めた人の誠から発せられた一言だろう。
この言葉に異議を唱える人間など、いるはずもない。
心配は杞憂だった。
『ねりこみ』は間もなく完成し、祭りの本番まで十分稽古を積むことができたのだった。
阪神・淡路大震災と取り立て屋K

テレビのスイッチを入れると黒煙が立ち上る神戸の街が映っていた。煙は一カ所だけではない。
画面が変わると、倒壊した多くの建物が無残な姿をさらしていた。
ただ事ではない。
阪神・淡路大震災の一報をテレビニュースで知らされたのは、1995年1月17日の早朝だった。
神戸と言えば、いやでも思い出さざるを得ない男がいた。
取り立て屋のKだ。この男が元銀行員だったと言うから驚く。
どこからどう見ても銀行員のイメージではない。
ワイシャツの第一ボタンをはずして、ネクタイはユルユル。
おまけに頭は丸刈りで、歪んだ口元がさらに迫力を加えている。
光のない鋭い目つきと出っ歯気味の口から吐き出す言葉には、人情のかけらもない。
他社の保証人になっていたため、私の会社はKが勤める会社に2千万円の債務を背負うことになった。
その返済方法を取り決める窓口になったのがKだ。
「担保はない」
「じゃ、手形を切れ」
「手形は切らない主義だ」
Kは実にしつこい取り立て屋だった。
「社長、1千9百万円にまけてやるさかい、38万円額面の小切手を50枚切りいや」
「これが最後や、もう妥協できへんで」
こんな時の関西弁ほど腹立たしいものはない。私は根負けした。
毎月38万円ずつ返済しなければならなくなったのだ。
バブル崩壊後、規模を大幅に縮小した私の会社にとっては、実に重い金額だった。
神戸が大震災に襲われたのは、それから数か月後のことだ。
震災の次の日、私はKの会社へ電話をしたが呼び出し音だけ鳴って応答はない。
その次の日も電話をしたが、やはり誰も出なかった。
電話の呼び出し音を聞きながら「あいつの会社なんて、潰れてなくなってしまえばいいのに・・・」との思いが心のどこかにあったのは否定しない。
だが、三回目も電話がつながらないと、心境は全く変わっていた。
「おい、おい、本当にダメになってしまったのかよ。まさかKやあの社長の身に・・・」
毎日、電話をかけ続けた。8日目か9日目くらいだった。
「もしもし」ようやくつながった。
しかも電話に出たのはK本人だ。
短い会話で終わったが、Kの声は明らかに沈んでいた。
それから1月ほどして、Kが予告もなしに会社へ現れたのだ。
帰るとき彼をエレベータまで送った。
「ワシみたいな奴でも心配して電話くれる人がおるんやな」
彼はそう言い残してエレベータに乗り込んだ。
それから2週間ほどして彼はまた会社へやってきた。
応接へ案内するなり、テーブルの上に紙袋を放り投げるではないか。
袋の中身はこちらが渡した小切手の束だった。
私は小学生の時に聞いた祖母の言葉を思いだした。
「心配ないよ。止まない雨は降ったことがないから」
学閥

山崎豊子が小説『白い巨塔』で、鋭くえぐった医学界の学閥。
「物語の中だけではなく、現実にある話なんだなあ。」
友人と話していて、そう思ったことがある。
牧野知弘氏が広くメデアに知られるきっかけとなったのは2014年、祥伝社からリリースされた『空き家問題ー1000万軒の衝撃』だった。
彼は東京・有楽町に事務所を置く『オラガ総研』の代表を務めるかたわら、これまで20数冊の書籍を出版し、講演で全国を飛び回る不動産業界では知る人ぞ知る存在だ。
今では週刊誌に連載を持ち、テレビのニュース番組にも登場する売れっ子だ。
その牧野氏が10月初旬、講演で札幌にやって来る。
講演が終わったあと、小樽で会うことになった。
久しぶりに二人で飲める。
私は彼と会うのを心待ちにしながら、4年前のことを思い出していた。
2019年に、彼が講演で札幌を訪れた時のことだ。
その時は私が札幌のすすきのに出向き、寿司屋で酒を酌み交わしたのだった。
気の合う二人が久しぶりに会ったのだから話題は尽きない。
だが、私は彼について一つ引っ掛かることがあり、いつか聞いてみようと思っていた。
話題が途切れかかったところを逃さず訊ねてみた。
「ところで牧野さんのお父さんは、なぜ東大に入ったことを怒っていたの」
彼の話によるとお父さんは医師で、後年は聖路加病院の病院長を務めた人だった。
とても優秀な医師だったのだ。
したがって、学界でもかなりの地位にいたであろうことは想像に難くない。
出身は東北大学医学部だ。
それゆえ職場でも学会でも、東大医学部出身の医師と何かにつけて衝突したのだという。
そんなこんなで、いつしかお父さんの頭の中には「東大イコール変な大学」の図式が出来上がってしまったのだろう。
子どもが東大に合格したら赤飯を焚き、親戚中をあげてお祝いする。
それが世間の相場だ。
息子の東大入学が対立の原因となるなんて、世にも珍しい親子ではないか。
それにしても、学閥という目には見えない壁と壁。
噂レベルでは知っていたが、生々しい実態を聞くのは初めてだった。
凡人の私には想像を超えた世界があるのだと、しみじみ思ったものだ。
いや、しみじみしている暇などなかったのだ、実は。
この話を終えるや否や彼の口から驚きの情報が飛び出したのだ。
「実は、まだ内緒だけど別府温泉に、インターコンチネンタルホテルの誘致に成功したんですよ」
それから数か月後の翌春、インターネットニュースが大々的に告げていた。
「別府温泉にラグジュアリーリゾート誕生へ!インターコンチネンタルホテルが進出」
やるねえ、牧野サン。
どうせ話すなら建設的で、ささやかでもいいから夢を持つ人との会話が、やはり楽しい。
酒も旨くなるのだ。
さて、今度の再会ではどんな話が飛び出すか。
実に楽しみだ。
銀座は後か、それとも先か?

未来を語り、夢を語る友と飲む酒は旨い。
そんな友人と久しぶりに再会できる。
札幌で講演することになったので終わったら一杯やろうと、友人の牧野知弘氏から連絡が入ったのは9月半ばだった。
「今回は僕が小樽まで足を延ばします」と言うから、うれしい。
斯界で大活躍中の彼から、今度はどんな話題が飛び出すか楽しみだ。
2023年10月初旬の夕方だった。
私はホテルへ迎えに行ったのだが、直前までリモートでテレビ朝日の取材を受けていたというから忙しい。
ホテルから歩いて10分ほどの居酒屋『百年坊』へ案内し、カウンターへ座った。
母と娘二人の女性ばかり一家三人で切り盛りする、魚の美味しい店だ。
飲み始めて1時間もすると、やはり出ました。
今回も夢いっぱいの話題が。
東大から13人の学生グループと副学長を引っ張り出すことに成功し、四国のある県と何やら企画が進行中だという。
村おこしや町おこしレベルではなく、県全体の活性化を目指しているのだ。
独特な彼の発想と大胆な行動力には度々驚かされるし、実にいい刺激にもなる。
話題が一段落すると彼は携帯を取り出し、百年坊のママに私とのツーショットを撮ってもらった。
「最近、銀座で千葉さんを話題にしながら飲んでいるんですよ。だから、これがいつも話しているチバちゃんだと銀座のお姉さんに写メールを送ります」
そういって、LINEを送信した。
自分のいないところで話題になるなんて、実に光栄なことではないか。
よし、それなら来年はどうしても、東京に行かなければならないだろう。
2020年に上京した時、牧野さんに連れて行ってもらった居酒屋がある。
新橋の赤レンガ通りだった。
あの美人ママの店でハイボールを飲んで、そのあと銀座に繰り出そう。
いや、待てよ。先に銀座へ行き、店がはねた後にホステスを引き連れて居酒屋へ行こうか。
どっちにしても、勘定はすべて稼ぎのいい牧野さん持ちだ。
「銀座は後にするか、それとも先に行こうか、それが問題だ」
他人の財布を当てにして、妄想は尽きないのだから我ながらヤバい男である。
インターネットラジオ

想像力を養い老いを防ぐには、ラジオを聴くのも有効な手段の一つではないだろうか。
ラジオを聴くことで、脳が活性化するとの研究結果があるくらいだから。
NHKのインターネットラジオ『らじる★らじる』が楽しい。
リアルタイムでなくとも、「聴き逃し番組」を探して好きな時間に聴けるから、私のような気まぐれにはピッタリだ。
主に小説や随筆の朗読を聴くのだが、これまで読んだことのない作家、作品に出会えるし知らない番組との遭遇もある。
先日、聴き逃し番組の一覧を眺めていたら、ふと目に留まったのが『国語辞典サーフィン』という番組名だった。
「なんだろう?」とクリックする。
聴いてみると、とてもユニークな発想の番組ではないか。
番組の趣旨は、このようなものだ。
「国語辞典はどれも同じように見えるかもしれないが、作り手には思いやこだわりがあって、意味の説明はそれぞれ個性的だ。
そんな知られざる辞書の魅力や、言葉の面白さを届けるのがこの番組だ」
例えばこの日、番組が取り上げた『美しい』の説明。
岩波辞典にはこのように記されている。
「目・耳・心にうっとりさせる感じを訴えてくるもの」
新解明国語辞典ではこうだ。
「いつまでも見ていたい、聞いていたと思わせるほどのもの」
三省堂辞典はこのように表現する。
「心が惹きつけられるほど音、形、色がいい、きれいだ」
まさに三者三様。
一つの言葉を説明する表現がこれほど違っていても、どれにも深く頷いてしまうから言葉の持つ意味は広く多彩なのだ。
実に新鮮な発見だった。
たちまちファンになってしまった。
番組を担当するのは、お笑い芸人のサンキュータツオと柘植恵水アナだ。
二人の補足や感想が、さらに番組を味わい深いものにする。
掛け合いもまた絶妙だ。
サンキュータツオがリスナーの質問に答える。
「〇〇さんのおっしゃる通り、異性のパートナーは一人に決めるべきだけど、辞典のパートナーは複数の方がいいですよ」
それを聞いて柘植恵水アナがポツリと漏らす。
「パートナーは複数の方がいいのか。なんだか辞典が羨ましい」
「なんだ、なんだ、それは?」。
たまげたことを言う女だとばかりに詰め寄る、サンキュータツオ。
「いえ、何でもありません。エヘヘヘ」。
ケセラセラとかわす柘植アナ。
「皆さまのNHK」らしからぬ、願望とも冗談ともつかない女子アナまさかの一言。
テレビでは、まずあり得ない発言だ。
カメラを意識しなくてもよいラジオだから、自由闊達になるのだろう。
これもまたラジオの魅力だ。
そして、聴いている方の想像も縦横無尽に広がる。
私は二人のことを全く知らない。
知らないが故に掛け合いを聴きながら二人の容姿や年齢など、様々なことに想像を膨らませる。
それが当たっていようが、的外れであろうが一向に構わないのだ。
想像すること、そのものが楽しいのだから。
『箱根駅伝』と『はやぶさ』

今や日本の正月に欠かすことのできない風物詩となった、箱根駅伝。
正式名は『東京箱根間往復大学駅伝競走』だ。
その名の通り、一つのルートを二日間かけて往復する競技に仕立てた先人の発想が素晴らしい。
東京から箱根まで駆け抜けて行くだけの一方通行ならば、これほどの支持を得られなかっただろう。
箱根まで行って、花のお江戸は日本橋に戻ってくるから、数々のドラマが生まれるのだ。
数あるドラマの中でも、人々の涙を誘うのが繰り上げスタートだ。
復路は先頭から20分以上遅れると、次の選手は真新しいタスキをかけての繰り上げスタートを強いられる。
駅伝はタスキをつなぐ競技だから、タスキを渡せなかった選手の無念は察して余りある。
大会終盤へ差し掛かった中継所で、毎年くり広げられる光景だ。
今年も戸塚中継所で、切ないドラマが生まれている。
レースの最後尾を走っていたのは、山梨学院大学だった。
戸塚中継所がテレビに映る。
8区を走る選手と9区の選手が待つ地点までは、すでに100mを切っていた。
必死にもがく同僚へ、タスキの到着を待つ選手が何度も声をかけて励ます。
沿道を囲む観衆も一体となって声援を送る。
タスキが渡るまで、もうすぐだった。
だが、勝負とは無情なもの。
あと30メートルを残して、規定の20分は過ぎてしまったのだ。
二人の選手が同時に聞いたのは、繰り上げスタートを告げる虚しい号砲だった。
これほど切ない30メートルが、他にあるだろうか。
だが、それでも9区の選手は黙々と前へ進む。
一日目に100㎞以上を駆け抜け、二日目にまた100㎞以上戻って来る競技だからこそ、このような人々の心を惹きつけて離さないシーンが毎回大会を盛り上げるのだ。
小惑星探査機『はやぶさ』も、まさにそうだった。
『はやぶさ』が、はるか遠い未知の惑星に到達しただけなら、日本中があれほどの興奮と感動に包まれることはなかったはずだ。
悠久の宇宙空間を7年間も航行し、様々な難題やトラブルに遭遇しながらギリギリのところで、何とか切り抜ける。
そうして幾多の困難を乗り越え、ついには小惑星の微粒子が詰まったカプセルを、この地球へ届けることができたからこその感動であっただろう。
また、はやぶさの帰還あればこそ、日本の宇宙開発は希望を持って次のステップに進めたのだ。
帰還は人に勇気を与える。
人は何かを待っている。
そして、誰かを待っているのだ。
懐かしいたった二度の会話

元米倉ボクシングジムの会長だった米倉健司さんが亡くなられた。
88歳だったというから天寿を全うされたのだろう。
私は学生時代、プロボクサーを目指して米倉ジムで練習に励んだことがあった。
当時は柴田国昭さんやガッツ石松さんが立て続けに世界チャンピオンになるなど、米倉ジムの第一次黄金時代ともいうべき時期だった。
ジムの広さは小学校の小さめの体育館ほどだったが、午後6時を回ると多くの練習生が集まり、その凄まじい迫力は外の通りまで伝わったものだ。
私はその混雑を避け、授業をさぼって昼の時間帯を選んだ。
昼のジムは閑散としていたから、夜では経験できない濃密な練習時間を過ごすことができたのだった。
入門したばかりでも、トレーナーが個別に声をかけてくれたし、時には質問にも答えてくれた。
世界チャンピオンの練習も間近で見ることができて「おお、すげえ」と驚きと興奮の中で練習した記憶が残っている。
米倉会長も時々顔を出して、ジムをゆっくりと歩き回っていたが、ある日、その会長に声をかけられたのだった。
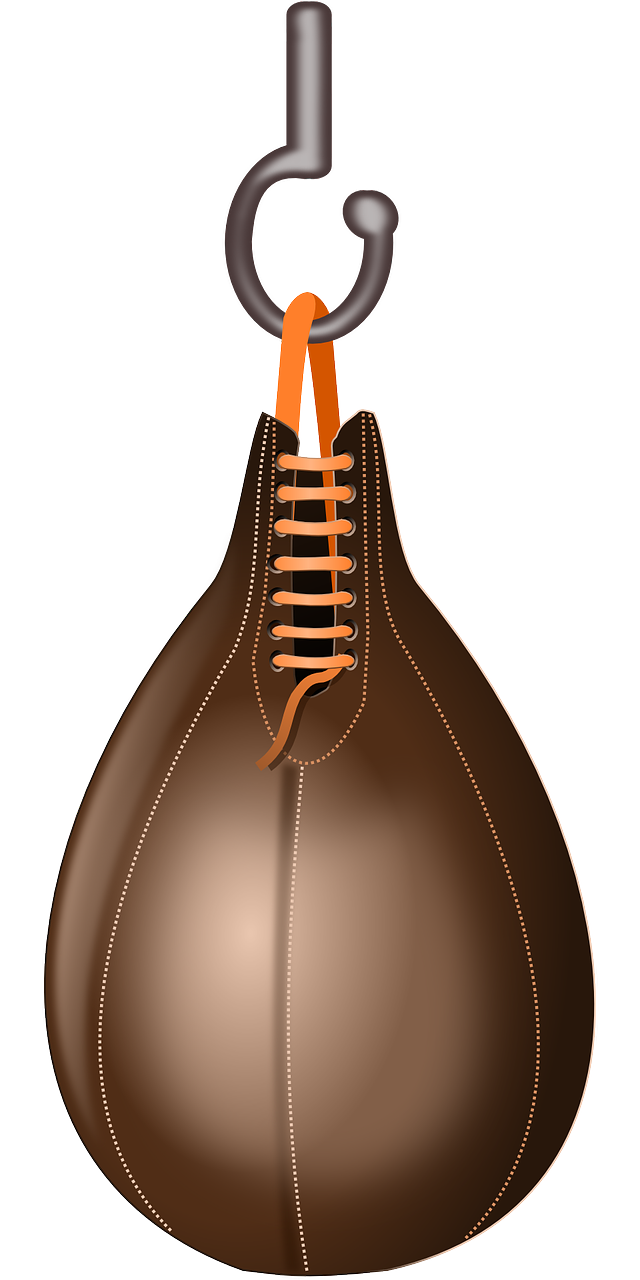
壁際で一人シャドーボクシングをしていると「君はパンチングボールを叩ける」と聞いてきた。
私のすぐ横にはパンチングボールがぶら下がっている。
「いえ、できません。」
「これ、難しいんだよなあ、8の字に叩くらしいけど、僕は今でもできないんだ」
そう言いながら会長は、ぎこちなくパンチングボールを軽くたたいた。
世界チャンピオンの座には届かなかったとはいえ、米倉会長は日本チャンピオンと東洋チャンピオンに輝いた男だ。
それにしては何と正直な人だろう。
他の練習生と話す会長の姿など見たことがないから、私はびっくりした。
雲の上でも歩くような感覚にとらわれたことを昨日のことのように思い出さずにはいられない。
それから数日後、また会長が近づいてきた。
「君はお尻が小さいから、減量には苦労しないタイプかな。これだけ身長があってフェザー級で出来たら、日本のボクサーでは貴重だな」
やはりこの時もニコニコと、穏やかに話かけられたのだった。
鍛え上げた人間が一対一で「生き物の本能」をむき出しにして戦うのがボクシングだ。
現役を引退したとはいえ、その百戦錬磨の強者がなぜあれほど穏やかなのか。
私はその直後、プロテストを目前にしてボクシングをやめてしまった。
だからボクシングにはそれほどの思い出はない。
だが、あの二度の会話だけは米倉会長の深い人間性に触れた思いがして、いつまでも忘れられないのだ。
合掌
なぜ、ボクシングを途中でやめたのかって?
それについては、いずれ近いうちに。
あの大波はどうして、たった一度だけ押し寄せたのか?

私は小学生の頃から素潜りが得意だった。
漁師だった父がアワビ採り専用のカギを用意してくれたのは、5年生の頃だったと思う。
あの頃、私が育った地域では、男の子であれば潜ってアワビやウニを採るのは当たり前だったが、専用のカギを持っている小学生は珍しかった。
だから私にとって、カギは水中眼鏡、冬のスキー板と並び三種の神器と言えるほど大事な宝物だったのだ。
海に潜り岩にくっついたアワビをはがす瞬間のスリルは、子どもの冒険心を十分に満足させてくれた。
だが、冒険心は気づかぬうちにエスカレートする。
「ああ、俺はこのまま死んでしまうのだろうか」
そんな危機に見舞われたのは、5年生の夏休みも終わりに近づいたころだった。
岩の隙間から大ものが見える。これまで採ったどのアワビよりも大きい。
隙間の奥は広いが、入口は狭い。
だがこの大ものは魅力たっぷりだった。何も考えずにカギを持つ手を突っ込む。
岩肌でこぶしを擦ったが痛みを感じる暇はない。
アワビは苦も無くはがれてカギに引っ掛かる。
だが、次の瞬間思わぬ事態に襲われたのだった。

手が抜けない。思いっきり引っ張っても隙間から抜けないのだった。
父からもらった宝のカギを断腸の思いで放したが、やはり抜けない。
もがいても、もがいても手首がこすれるだけで時間は刻一刻と過ぎていく。
呼吸が苦しい。
意識も遠のいていく。
「俺は、このまま死ぬのだろうか?」
あきらめにも似た心境に陥った次の瞬間だった。
身体がフワッと浮く感覚に襲われたのだ。
水中でバック宙返りを打ったのだった。
両脚が誰かに持ち上げられたように身体が後ろ向きにくるりと一回転した。
その勢いで、岩に挟まれた手は抜けていた。
水上に顔を出し思いっきり息を吸ったのだが、何が起きたのか全く理解できない。
大波が来たのだろうかと、あたりを見回したが海は相変わらずゆったりと横たえている。
呼吸を整え、大事なカギを探しに潜るとすぐに見つかった。
カギは指先でつまみ出せたのだが、大ものクンがすぐそこでモゾモゾしているのが見えた。
全く懲りない子どもだった。執念だったかもしれない。
「おっ、これなら採れる」
アワビは吸盤のように固く吸い付いたところをはがされると、すぐには元のように吸い付いたり、速く逃げることはできない。
一度カギで引き寄せられたアワビは4、50㎝あった柄の長さでけで、今度は十分届いたのだ。
海は平然と穏やかだったが、大波が押し寄せたこと以外に身体が回転した理由は考えられない。
子どもとはいえ、海中の両脚を持ち上げるのはかなり大きなうねりが必要だ。
「もしも、あの波が来なかったら」と、あの時は考えた。
だが、今は違う。
「どうして、あの時に限って大きな波が、たった一度だけ押し寄せたのか?」と考えるのだ。
イワナは何匹釣れた?

中学二年のゴールデンウィークだった。
隣の集落から三人の同級生がやってきて、近くの渓流へイワナ釣りに出かけることになった。
「イワナがごっそり釣れたら、どうしよう」「熊が出るかもなあ」。
三十分ほどの道のりをたわいもないことを言いながら歩くのが、たまらなく楽しい。
だが、この時はまだ、あんな思いをするなんて想像もしていなかった。
渓流に糸を垂らしてから、もう一時間はとっくに過ぎていたが、誰の竿にも全くあたりがない。
石の上を飛び回って、あっちこっち場所を移動するが、何の手応えもなく時間だけが虚しく過ぎていく。
もう少し上流へ行こうと、釣り針を上げた時だった。
近くの藪がガサガサと大きな音を立てた。息を飲んで振り向く。
他の三人も身を固めて藪を凝視する。
次の瞬間だった。
バサバサと藪が大きく揺れる。勢いよく飛び出してきたのは大型の鳥二羽だった。
「なんだ、鳥かよ」。
誰も口にしないが、四人の想像した動物は同じはずだ。
安堵の空気が流れる。
それにしても、イワナは釣れない。
気配さえ感じないのだ。
二時間もたつと他は誰も糸を垂らしていなかった。
笹舟を作って水に浮かべたり、向こう岸に石を投げたりして、それぞれ勝手気ままに遊んでいる。
だが、自分は釣りをやめられない。
隣の集落からわざわざ友人がやってきたのだ。
いわば自分はホスト役だった。
せめて四匹釣って、一人一匹ずつ分けたい。
いや、自分の分はいらないからせめて三匹だけでも。
それがついには「一匹だけでも釣れてくれー」と悲痛な思いになっていた。
時間は容赦なく過ぎて「もう帰ろう」の声が上がる。
あきらめざるを得なかった。
ただの一匹も釣れないなんて。
ああ、世の中にこんな無情があっていいものか。
世界中の悲しみを一人で背負ったような気分だった。
ホストの面目丸つぶれだが、自然には勝てない。
悲しみに打ちひしがれながら、竿を畳んだ。
「ああ楽しかった」
「面白かった」
「熊に会えずちょっと残念」
三人は晴れ晴れと笑う。
その言葉を聞いたとたん悲しみなんて、一瞬にして五月の高い空の彼方へ吹き飛んで行ってしまった。
のどかな少年時代だった。
イワナを一匹も釣れなかった事が、人生最大の悲しみに思えたのだから。
NHKニュースで「今日から飛び石連休が始まりました」と伝える時代だった。
果たして駅名は?

全く頼りない記憶力だ。
昭和47年か48年だったと思う。
小海線に乗ったことがあった。
山梨県小渕沢駅から長野県小諸駅まで八ヶ岳の麓を約79㎞にわたってのんびりと行くローカル線だ。
新聞配達をしていた学生時代は、春分の日が待ち遠しかった。
当日の夕刊と次の日の朝刊が休みだから、ほぼ毎年1泊旅行に出かけたものだ。
その年は友人と二人で、長野県の松本城に行くことに決めていた。
吉祥寺駅で待ち合わせて中央線で八王子まで行き、そこから中央本線に乗り換えて松本まで行く計画だったように記憶している。
計画といっても決めているのは目的地と乗る電車くらいで、いつものように宿の予約もしていない。中央本線にさえ乗れば松本にはたどり着くだろうという気楽な旅だ。
ところが、甲府駅に着いたあたりから計画はあやしくなった。
思ったよりも中央本線の各駅停車はのんびりと走っていたのだった。
「このままだと松本に着くのはかなり遅くなる。
夜になってから宿を探すのは大変だ」と友人が言う。
そこで、小渕沢駅で小海線に乗り換えて小諸に向かうことにした。
しかし、小海線で千メートル超の高原を走るのは楽しかったが、小諸もまた遠かったのだ。
日が落ちて八ヶ岳も見えなくなり途中下車することにした。
このとき降り立った駅名はずーっと『海ノ口温泉駅』だと思っていた。
だが、ふと思い出してネットで調べてみたら『佐久海ノ口駅』になっているではないか。
ウイキペディアで調べても駅名が変更になったとは書かれていない。
駅が所在する南牧村役場に問い合わせたけれども、若い男が電話の向こうで「駅名が変わったなんて聞いたことありません」とにべもない。
JRのお嬢さんは電話を保留にしてかなり時間をかけて調べてくれたが、やはり駅名の変更は確認できないとのことであった。
記憶なんて頼りないものだ。
駅名はおぼつかないが、翌朝、下駄で踏みしめた名残雪と、前夜、宿を丁寧に教えてくれた駅員さんの親切な笑顔だけは、記憶から消えることはない。
喜怒哀楽

月に帰る直前、かぐや姫はこのように言い残している。
「あの都の人は、とても清らかで美しく、老いることもないのです。もの思いもありませぬ。」
あの都とは、自分が帰るべき月の世界だ。
かぐや姫は、地球上の人間が渇望してやまない不老不死の世界からやって来て、そして帰って行くのだ。
だが、そのあとに続く言葉が、あまりにも衝撃的ではないか。
「そのような所へ行くことは、嬉しいとも存じませぬ」
彼女は人々が憧れてやまない理想郷に、実は戻りたくなかったのだった。
なぜだろう。
不老不死だから病気も生活苦もなく、死の恐怖もない。
これほど幸せないことはないだろうと考えがちだ。
だが待てよ。
不老不死はまた、不変の世界でもある。
昨日も今日も、明日も明後日も未来永劫に事件も事故も起こらない安穏で平和な日々。
美の極致でもあるから彼も彼女も、あの人もこの人もみんなが清らかで美しく、在るものすべては清浄で穢れなく、あらゆることが平等なのだ。
不老不死は苦のない世界であらねばならない。
苦によって死を願う者がいたら、不死の意味がなくなってしまう。
故に、そこで暮らす人々に一切の違いや差別は、存在しない。
他人との優劣こそが、苦の根源だから。
能力にも所有物にも差はないのだから比較のしようがないので、優越感も劣等感もなく、必然として嫉妬や羨望の感情もない。
だから「・・・もの思いもありませぬ」となる。
つまり、喜びや悲しみの感情が生まれる必然性はなく、すべて満たされているから思考そのものが必要ない、ということだろう。
いわば『寂』の世界だ。
平安の都で、かぐや姫が大勢の男たちからチヤホヤされたようなことも、その世界ではありえないのだ。
表現できないほどの美貌を誇っていても、どれほど光り輝いていようとも称賛されることはなく、誰からも羨望の眼差しを向けられることのない世界。
帰るのを渋った彼女の気持ちがわかる。
一度味わった喜びや楽しさの感情を忘れることができないのは当然だろう。
竹取物語には、かぐや姫が地球へ来たことも月に帰ったことも、自分の意志ではなかったと書かれている。
「ならば今度は自らの意志でこの地上に戻って来てください」と、私は月に向かって呼びかけるのだ。
彼女には生老病死の混沌たるこの世界で、『喜怒哀楽』を心行くまで味わって欲しいと思うから。
とん平の天津麺

高校入試の前日、私は担任の先生と二人でラーメン屋の暖簾をくぐった。
店の名を『とん平』といった。
初めて座ったカウンターからラーメンを頼もうと思っていたら、先生が「天津麺を食べてみないか。旨いから」と薦めてくれた。
天津麺が目の前に運ばれてくる。
これはすごい。
まだ卵が貴重品だった時代、憧れの丸い卵焼きがラーメンの上にてんこ盛りではないか。
しかも、ただの卵焼きではない。
カニがたっぷりとは入っている。
もうそれだけでも衝撃なのに、湯気と一緒に顔に降りかかる初めての匂いがたまらない。
喉をごっくんと鳴らして割り箸を持ったまま、じーっとみつめていると先生がビールを飲み干しながら「冷めないうちに食べな」と促す。
丼と卵焼きの隙間から麺を一つかみ取り出して口に運ぶ。
それから汁をすすり、待望の卵焼きを一口含む。
すべてが初めての経験だ。
あまりの美味しさに中学3年生の五臓六腑が躍った。
この時、一瞬目をつぶったような記憶が残っている。
目を見張るほどの美味しさに、思わず目をつぶってしまったのだ。
そこから先はよく覚えていない。
もう夢中で食べたに違いなかった。
丼の底が乾くほど汁を飲み干したのだけは覚えている。
麺も出汁もカニとネギの入った卵焼きも点数のつけようがない。
星だって5つでは済まない。
満天の星を全部あげても惜しくはなかった。
私が高校を受験したのは昭和41年の冬だ。
生まれ育った神恵内村の端から高校のある岩内まで行くには当時、陸の交通機関はなく69トンの定期船『神威丸』が唯一の交通手段だった。
数人の受験生を陸の孤島から岩内まで、担任の先生が引率してくれたのだ。
19歳で上京してからこれまで衝撃の味を再びの想いを抱き、首都圏を中心に天津麺を食べた店はゆうに100軒を超える。
美味しい店はたくさんあったが、『とん平』を超える感動には出会っていない。
平成になって間もないころ、帰省した私は子どもたちにあの時の天津麺を食べさせたいと思い、たずねてみたが岩内町の浮世通り周辺は様変わりしていた。
どこを探しても『とん平』はない。
忘れられない初めての天津麺を思い出しながら、喉をごっくんと鳴らして立ち去るよりほかなかった。
「君はボクシングの他にやりたいことがあるか?」「はい、あります」

二人は寿司屋のカウンターに並んで座っていた。
30歳半ばの男が言った。
「君はボクシング以外、他に何かやりたいことがある?」
「はい、あります」
答えたのは21歳の青年だ。
男は少し間をおいて言う。
「じゃあ、ボクシングはやめた方がいい。僕も今日から一切教えない」
青年は一瞬、戸惑った。
だが、そのあとに男が言い放った言葉に納得した様子で、はっきりとした口調で答える。
「やめます。」
ボクシングに関する二人の会話は、これで完全に終わった。
その後も二人の交流は続いたが、両者ともにボクシングの話題は一切口にしなかったのだ。
当時21歳の学生だった私は、プロボクサーを目指して米倉ジムに入門した。
たまに顔を出すスナックの常連だったのが、元プロボクサーの高宮さんだ。
マスターから紹介されたその日のうちに薄暗い路地に連れ出され、シャドーボクシングをしてみろというほどボクシングには熱い人だった。
その後も、店で会うたびに路地裏で指導を受けた。
スナックと軒を並べる小料理屋の女将が「まるで”あしたのジョー”ね」と顔をのぞかせて笑う。
いよいよプロテストが間近に迫ったある日、高宮さんから連絡がありスナックへ行くと常連が顔をそろえていた。
「この身長でフェザー級とは、本当に楽しみだ」
小柄な高宮さんは自分のことのように誇らしげな表情で、常連客に言う。
まったく同じセリフをつい最近、米倉ジムの会長に言われたことがあり、私も内心得意だった。
「ちょっと二人だけで食事に行こう」
直後に、そう誘われて寿司屋の暖簾をくぐったのだった。
元プロボクサーの高宮さんは、右目を失明している。
フライ級の日本チャンピオンに挑戦した試合でパンチを浴び、右目の光を失ったのだ。
その人が「プロボクシングは、他にやりたいことがあるのに通用するほど甘くない。
命をかけられないならやめろ」と言ったのだ。
矢のような鋭い音を立てて、胸にグサッと突き刺さった。
私に続ける選択肢はなかった。
この日から、私はことあるごとに考え、模索してきた。
「プロとは何か?」「自分は何に命を懸けるべきか?」。
そして、もう半世紀も経つが今なお、明確な答えを見つけられないでいる。
だが、決して答えをあきらめたわけではない。
今日も問い続けている。
[contact-form][contact-field label=”名前” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”メール” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”サイト” type=”url” /][contact-field label=”メッセージ” type=”textarea” /][/contact-form]




