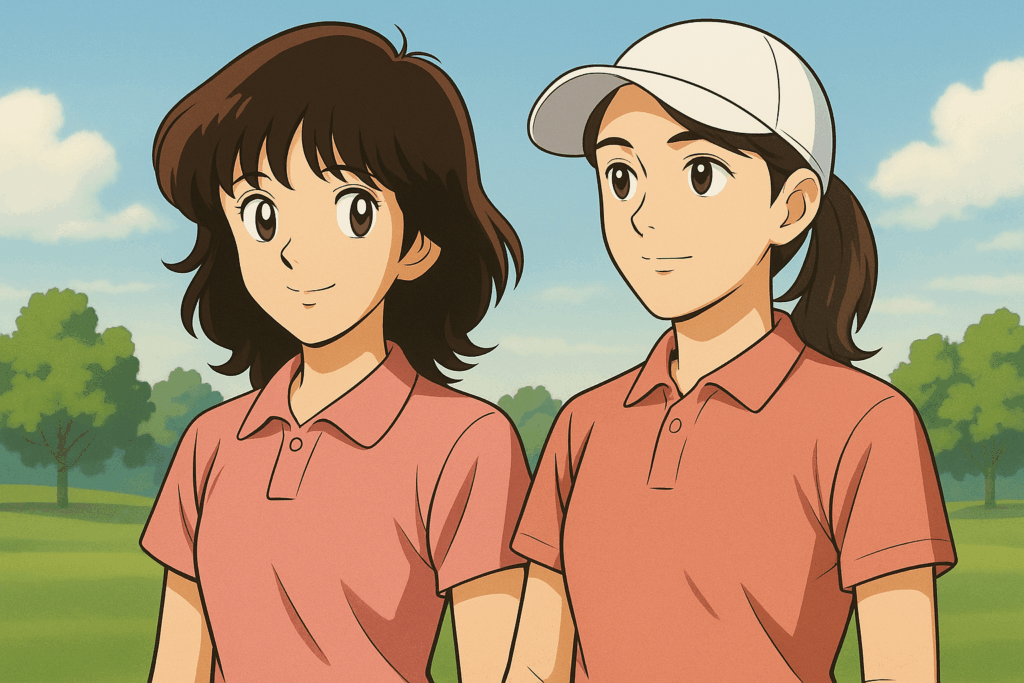日本のゴルフ人口は1994年のピーク時から現在(2022年〜2023年)にかけて、約40%から60%の減少を記録しています。
減少幅は、各調査機関のデータによって多少の差はありますが、長期的な減少トレンドは共通しています。
2024年の全国ゴルフ場入場者数でも、前年より2.3%減少して4,848万1,410人だったと報告されました。
猛暑などが原因とされていますが、物価高や円安でプレー単価が上昇し、家計の余力が削られたことも否定できません。
ゴルフはスポーツであり娯楽でもありますが、余暇の縮小は社会全体の健康を映す鏡でもあると言えます。
そして、その背後には、「緊縮財政」という100年前から続く設計思想が潜んでいます。
緊縮は倹約の美徳と喧伝されますが、大きな間違いです。
「緊縮財政」は労働者の賃金を抑え込み、富裕層の利益を肥大させ、社会を分断してきた“格差製造装置” なのです。
緊縮財政は「節度」ではなく、格差を固定する仕組み
![]() 多くの人が「緊縮=倹約の美徳」と信じていますが、実態は正反対です。
多くの人が「緊縮=倹約の美徳」と信じていますが、実態は正反対です。
政府が支出を削れば需要は縮み、企業は賃上げの圧力から解放されます。
労働生産性が上がっても賃金は据え置かれ、労働分配率は低下します。
その一方で、資産を持つ層は株式や不動産収益で利益を積み上げ、格差は拡大してしまうのです。
さらに緊縮は、社会保障や公共サービスの削減とセットで進められます。
福祉や教育投資の削減、消費税の増税は低所得層ほど家計を直撃し、世代を超えて格差を固定化させます。
考えても見てください。
消費増税に反対する大企業経営者をあなたはどれほど知っていますか。
富裕層から湧き上がる「消費増税反対」の合唱を聞いたことがありますか。
不思議なことに、日本のメディアもほぼ反対しません。
100年前に設計された「緊縮の思想」
第一次世界大戦後、イギリスとイタリアで緊縮は制度化されました。
イギリスのホートリーやイタリアのパンタレオーニらが作り上げた「経済は中立で科学的」の言葉は、政治的な選択を覆い隠してしまったのです。
では、「経済は中立で科学的」と国民に思わせることが、なぜ政治的選択を覆い隠したと言えるのか、それを具体的に説明します。
1,「科学的必然」に見せれば反対しにくい
もし「賃金を抑えるべきか?」「公共支出を削るべきか?」を政治の場で議論すれば、必ず労働者や市民から反発が出ます。
しかし「これは経済学の法則であり、自然科学と同じく不可避だ」と言われると、「政治的対立の余地がない」と思わされ、反対の声を抑え込むことができます。
2,「中立」の衣をまとったイデオロギー
本来は特定の階級に有利な判断でも、「科学的に中立」と見せることでイデオロギー色が薄まり、あたかも誰の利益にも偏っていない普遍的な真理のように受け止められます。
これが「政治の外に置かれる」という意味です。
3,スピードと実行力が増す
民主主義的な手続きや労働者との交渉を経ずに、「経済法則だからやるしかない」として処理できるため、政策は速やかに実装されます。
これは政治的調整のプロセスを迂回する仕組みです。
角度を変えて表現すれば、「資本階級が労働者階級から搾取する」理論が世界を支配しているのです。
「緊縮」をお題目として、国家がそれを強固に後押しいている構造です。
では、「緊縮」がどうして格差を拡大するのか、そのメカニズムを具体的に見ていきましょう。
緊縮財政下で富裕層の富が増えるメカニズム
1. 富裕層は「労働収入」に依存していない
労働者:収入の大半は給料。
緊縮で需要が縮み、賃上げが止まると収入が伸びない。
富裕層:収入の大半は配当・利子・不動産収入など「資産からの収益」。
→ 緊縮下でも給料が上がらなくても、資産があればその運用益で収入を増やせる。
2. 利益率は下がらず、むしろ高まる
緊縮で労働コスト(賃金)が抑えられると、企業の利益率が上昇します。
企業の利益が増える → 株価が上がる。
株を多く持っているのは富裕層 → 富の増加につながる。
つまり「賃金を削った分がそのまま資本家の利益に回る」構図です。
3. 金融資産への資金集中
緊縮で需要が弱いと、設備投資は増えません。
余った資金は株式市場や不動産に流れやすい → 資産価格が上昇する。
資産をすでに持つ富裕層は、この値上がり益を享受できます。
逆に資産を持たない層は、家賃や物価上昇でむしろ負担増になる。
4. 税制や政策も富裕層に有利
緊縮政策のもとでは「増税」といえば消費税が中心になりがちです。
消費税 → 所得に関係なく同じ税率 → 低所得者ほど負担が重い。
富裕層は株や資産からの収益で生活 → 相対的にダメージが少ない。
結果として、低中所得層の負担が増える一方で、富裕層はますます余力を増やす。
労働者の賃金は抑えられ、経営者の収入が増大する現状
日本ではバブル経済崩壊後を「失われた○○年」と表現します。
その間、労働者の平均賃金は、ほぼ上がっていません。
しかし、史上最高益を更新している大企業はたくさんあります。
また、労働者階級の賃金は上昇していないのに、経営者側である社長や役員の収入は増大しているのです。
40年近くも「緊縮」に走った結果が、明らかな形で顕在化しています。
それでも「税制規律」が叫ばれる不思議。
ホートリーやパンタレオーニらが作り上げた「経済は中立で科学的」の、響きだけは心地よい理論。
100年後のいまも世界の政治経済はその設計図通りに進行しているのです。
労働者はこのまま不勉強で無責任な官僚や政治家たちに、洗脳され続けるよりほかないのでしょうか。
日本で繰り返される「財政健全化」の呪文
日本でも同じ構造が繰り返されています。
・プライマリーバランス黒字化の目標
・逆進的な消費税の強化
・国債残高の数字だけを独り歩きさせる、片手落ちの議論
これらは「国の家計簿を整える」というイメージで語られますが、国家は家計と違い、需要を創出し未来へ投資できる存在です。
にもかかわらず、政治家や評論家は「規律」を唱え続け、需要を創出しない方向へと舵を切り続けます。
結果として賃金の上昇が抑えられ、家計の余力は痩せ衰えて格差が深まっていくのです。
逆に企業の内部留保は増大し、労働者の気づかぬ間に株式配当などで富裕層を潤しているのです。
慣例にとらわれ、固定観念でしか物事を見ることのできない者たちが発言力を持つ社会の悲劇が、ここにあります。
革新を唱えながら資本家の仕掛けた巧妙な罠に1世紀以上も気づかない庶民派の勉強不足、発想の貧困、洞察力の乏しさ。
彼らこそが格差を助長し、労働者階級を追い詰めるのです。
その悲しい現実が、目の前に存在しています。
何という皮肉でしょう。
国家の会計と家計簿が全く違う理由
1. お金を「生み出せる」かどうか
家庭:収入は給料や年金など、外部からもらうもので限られる。
自分でお金を発行することはできない。
国家(特に自国通貨を持つ国):国債の発行や中央銀行の信用を通じて、お金を供給できる。
つまり「通貨を発行できる主体」である。
2. 支出の意味
家庭:支出は純粋に財布からお金が出ていく行為で、減るだけ。
国家:支出は国民全体の需要や雇用を生み出す投資。
たとえば公共事業や教育支出は、将来の経済成長や税収増につながる。
3. 借金の性質
家庭:借金を返せなければ破産。
返済能力の範囲でしか借りられない。
国家:国債は自国通貨で発行する限り返済不能にならない(自国通貨建てなら返せる)。
むしろ国債は「国民の資産」として銀行や年金基金に保有される。
4. 時間軸の違い
家庭:人生の時間は有限であるため、老後や相続までを考えて「赤字は悪」となる。
国家:寿命はなく、世代を超えて資産や負債を引き継げる。
未来への投資として赤字を出すことが合理的な場合も多々ある。
家計簿と国の会計は明確に違う
家庭の家計簿は「いかに支出を収入の範囲に抑えるか」の発想で動きます。
一方、国家の会計は「いかに支出で経済全体を成長させ、国民生活を豊かにするか」の発想で設計されるべきものです。
だからこそ「国の会計を家計簿のように扱う」こと自体が誤解であり、このような考えが緊縮論を広げる大きな原因になっているのです。
現実を冷静に見つめる力があれば理解できることです。
「財政緊縮論」や「財政規律」にこだわった政策が続く限り、格差は拡大するばかりです。
一時的に景気が良くなったとしても、その間でさえ格差は拡大し続けます。
この30数年間、日本人はその現実を目の当たりにしてきたはずです。
しっかりと現実をみつめましょう。
しかし、日本政府による一般会計の推移を見て、「日本は緊縮財政ではない」という人たちも多く存在します。
日本の人口がピークを迎えた2008年度は約84兆円だった国家予算。
それから17年後の2025年度には115兆円になっています。
毎年編成される補正予算の規模も拡大しています。
アベノミクスの第2の矢として積極財政を唱えた安倍内閣でさえも、コロナ禍前の補正予算の規模は平均3兆円程度でした。
これがコロナ禍で大きく拡大されます。
そして、コロナ禍が終った後も縮小されません。
近年は10兆円規模が当たり前となり、2024年12月に編成された補正予算も13.9兆円と、とても大きな額になっています。
けれども、これを以って「緊縮財政ではない」と断言するのは、早計でしょう。
表面的な数字のみを見ているから、そのような考えになるのです。
名目規模は拡大しているが、それでも「緊縮」と言える理由
一般会計は2008年度:約84兆円 → 2025年度:約115兆円と名目では拡大しています。
それでも日本が「緊縮的だ」と評価されるかどうかは、金額の大小ではなく、政策スタンス(どこに配分し、景気局面に対してどう振る舞ったか)で決まるからです。
以下に論点を整理します。
1. 名目の増加と「実質スタンス」は別物
緊縮財政とは、単に歳出総額が減ることではなく、景気や需要に対して十分な財政出動を避け、均衡や債務抑制を優先する姿勢を指します。
名目額が増えていても、景気に対する財政の押し上げ(財政インパルス)が弱ければ、実質的には緊縮的です。
2. 伸びの中身は「社会保障の自然増」
高齢化で年金・医療・介護は自動的に膨らみます。
これが総額を押し上げる一方、公共投資・教育・子育て・科学技術など将来の成長と賃金形成に効く分野は長く抑制されてきました。
総額は増えても、成長と所得を押し上げる質の支出が不足すれば、家計の余力は戻りません。
3. 「増税&負担増」で家計を冷やす設計
この間、消費税の引上げ(1997年、2014年、2019年)が繰り返され、社会保険料負担も上昇しました。
逆進的な消費課税や負担増は可処分所得を削り、需要を弱めます。
支出が増えていても、家計を冷やす設計なら景気全体は緊縮方向に働きます。
4. 公共投資・教育投資の「痩せ」と賃金停滞
労働生産性や賃金を押し上げる投資が細ると、企業の賃上げ余地・圧力が弱まります。
結果として実質賃金の停滞が定着し、余暇・文化への支出(ゴルフなど)も削られやすくなります。
5. PB(基礎的財政収支)黒字化目標という「枠」
日本の財政運営は長くプライマリーバランス黒字化を最上位に置いてきました。
この枠を優先すると、景気悪化時でも歳出拡大・減税に躊躇が生じ、回復局面では早期に引き締めへ戻る――プロサイクリック(景気逆行)な運営になりがちです。
これは典型的な緊縮バイアスです。
6. 「財政インパルス」で見ると抑制的
財政の景気押し上げ・押し下げは、歳出入の変化を通じた財政インパルスで評価します。
名目の積み増しがあっても、増税・負担増や歳出の中身の入れ替えでネットの押し上げが小さければ、実体経済には緊縮的に働きます。
7. 生活実感への帰結:実質賃金・可処分所得・需要
結果として、実質賃金や家計の可処分所得の伸びは鈍く、民間の需要が慢性的に弱い状態が続きます。
総額が増えても、家計の懐が温まらない=需要が戻らないなら、政策スタンスとしては「緊縮」寄りだと言わざるをえません。
8. 反論への短答
▲反論:「115兆円まで増えているのに緊縮のはずがない」
●答え:総額ではなく配分とタイミングが問題。
社会保障の自然増と増税で相殺され、成長に効く分野が痩せている。
▲反論:「歳出拡大はインフレを悪化させる」
●答え:重要なのはどこに投じるか。
ボトルネック解消・所得底上げ・将来の供給力に資する投資は、持続的な安定につながる。
小括:数字の“増”とスタンスの“引き締め”は両立する
2008年度84兆円→2025年度115兆円という名目の増加は、主として社会保障の自然増に起因します。
一方で、PB黒字化優先・消費増税・将来投資の抑制という運営は、需要と賃金形成を弱め、家計の余力を削る方向に働いてきました。
ゆえに、日本は「見かけの規模拡大」と「実質の緊縮スタンス」を同時に抱えている――これが実態です。
なぜ格差批判者まで緊縮を叫ぶのか
ここに、大きな矛盾があります。
格差を批判する政治家や評論家が、同時に「財政規律」を強調するのはなぜか。
理由は三つあります。
1. 「赤字は悪」という単純な物語が、彼らの中に根付いてしまっている。
2. 緊縮を基本とする官僚機構(特に財務省)の強い影響を受ける。
3. メディアや有権者が「バラマキ」を嫌うため、緊縮を語る方が安全で受けが良い。
この結果、無意識のうちに格差を強化する側に回った発言を繰り返してしまうのです。
これでは多くの国民が「給料が上がらない」と愚痴りながら、不勉強で無責任な者たちにミスリードされているのですから、浮上のきっかけをつかめないのは当然なのです。
バフェットの言葉が突きつける現実
この発言は、格差が自然現象ではなく制度的に作られていることを示しています。
つまり、「緊縮財政」が富裕層に大きく味方している、とバフェットは断言しているのです。
緊縮の枠組みを維持する限り、労働分配率は下がり、資産収益を享受する富裕層だけが「勝ち続ける」ことになります。
ゴルフ人口減少は、その社会構造のひとつの帰結にすぎません。
よく例えられる言葉に「金融は経済の血液」または「産業の血液」があります。
金融とは簡単に言えば「お金」です。
緊縮財政下では血液にあたる、そのお金の循環が細ります。
これで健康体を維持せよと言われても無理です。
そしてグローバル化のこの時代、本当の富裕層は一国のみ、あるいは自分の母国だけで蓄財しているわけではありません。
海をまたぎ、複数の資産形成パターンを有しているのです。
日本の経済が停滞しても、先細りになっても資産を増やす方策に事欠きません。
けれども、労働に専念している者の収入源は一つだけ。
かくして、格差は拡大するばかりです。
戦後の日本は緊縮財政と無縁の路線を突っ走り、世界から奇跡と言われた「高度経済成長」を成し遂げました。
では、どの政権から緊縮へ舵を切り始めたのでしょうか。
次章ではその軌跡を見ていきます。
経済学者やテクノクラシーはなぜ資本に従うのか
「緊縮」や「財政規律」が“科学的に正しい”と称される背後には、政治・制度・学術の力学が折り重なっています。
ここでは、経済学者や官僚(テクノクラシー)が資本家に有利な学説を信奉しやすい理由を、4つの観点から整理します。
1. パトロンと制度的バイアス
研究費・寄附講座・政策委託・ポストなど、学術と官僚のキャリアはしばしば政府や財界との関係で形成されます。
資本に有利な理論を掲げるほど、資金・評価・発言機会が得やすい誘因構造が働きます。
逆に分配強化や反緊縮は「急進的」「非現実的」とレッテル化され、周縁に追いやられがちです。
2. 「科学的中立」という自己像
経済学はしばしば物理学のような中立的学問として語られます。
「市場は効率的」「赤字は悪」という単純な命題は、数式モデルで美しく表現しやすく、“科学的必然”に見せる力を持ちます。
実際には価値判断(誰の負担を増やすか)が含まれているのに、それが不可視化され、政治的争点が脱政治化されます。
3. 利益と思想の一致(道徳化の罠)
資本に有利な学説は「規律」「自助」「市場の秩序」と結びつけられ、道徳的に優れた態度として語られます。
学者・官僚自身も“善”を語っている感覚を持ちやすく、利害(資本の利益拡大)と思想(規律の美徳)が一致することで、理論の自己正当化が強化されます。
4. 学界の同調圧力と異端排除
主要ジャーナル・査読・採用・研究費配分は主流派の評価枠組みに依存します。
反緊縮・分配重視・制度派などのアプローチは「非主流」とされ、掲載・昇進・研究資金で不利になりがちです。
若手ほど生存戦略として主流理論に順応し、結果として資本に有利なパラダイムが再生産されます。
結論:個々人の悪意というよりも、資金・評価・道徳・制度が形づくる構造的な誘因が、テクノクラシーを資本有利の学説へと押し流します。
だからこそ、「科学」を名乗る主張に埋め込まれた価値判断を可視化し、民主的な選択として議論し直すことが重要です。
官僚、学者といえども一人の人間。
出世したい、立場を守りたい、などの欲望は当然あります。
いや、エリートだからこそ人一倍強いのが当たり前なのです。
国民大衆が、彼らエリートの言葉を鵜吞みにすることで格差は拡大し、支配体制がより強固になっていくのです。
症状としてのゴルフ人口減少
このブログはゴルフがテーマです。
したがって、緊縮がゴルフに与える影響についても述べておきたいと思います。
2024年のゴルフ場利用者数では、一人当たりの回数も減っているので「余暇が削られる社会」の一端を表しています。
スポーツや文化は、家計に余力があって初めて花開きます。
もしこの縮小を「若者がゴルフを嫌っている」などと短絡的に説明するなら、格差を生み続ける本質を見落とすことになります。
ゴルフは一例に過ぎず、余暇の全体が縮小しているのです。
収入が増えず、物価が上がるのですから当然のことです。
ではなぜ、テクノクラシーや経済学者は、資本家側に有利な財政理論から離れられないのか。
その秘密を暴きましょう。